 能は卑俗な猿楽から徐々に発達したものである。それが室町時代に世阿弥の手によってひとつの芸能の型に高められ、これを足利尊氏が保護し、プロデュースしたことで大衆化した。ときの都は京都。奈良・興福寺では野外上演が催され、数千人の観客が詰め掛けた。言い伝えを信じれば世阿弥という人は美男子だったから、能というものは、美しい男に観衆がうっとりするようなショーだったのでしょう。ここらへんがうらやましい。
能は卑俗な猿楽から徐々に発達したものである。それが室町時代に世阿弥の手によってひとつの芸能の型に高められ、これを足利尊氏が保護し、プロデュースしたことで大衆化した。ときの都は京都。奈良・興福寺では野外上演が催され、数千人の観客が詰め掛けた。言い伝えを信じれば世阿弥という人は美男子だったから、能というものは、美しい男に観衆がうっとりするようなショーだったのでしょう。ここらへんがうらやましい。
江村夏樹
みなさんは、こんなふうにおもうときはないでしょうか。どうせ失敗してしまったのなら、それが宿命的なものであって、自分の力でどうとりかえしのつくものでもないと考えたほうが、諦めがつきやすい、つまり気が楽というようなときが。なぜ気楽かといえば、自分の力でどうにもならない以上、みなさんはなにもしなくていいからであります。これは怠惰と無気力の証拠でありますが、これが徹底しますと、いっそのこと早く失敗してしまったほうがいいと望みだすのです。失敗してから、そのあとで宿命の理由づけを求めるのではなく、まだ失敗しないうちに、早く失敗と破滅とにみずからいそごうとするのです。そして、この失敗と破滅とに急ぐ自分の気もちを理由づけするために、宿命を、あるいはそれに似たものを、あらかじめ用意しておこうとするのです。いきなりひとの文章の抜書きで驚きましたか。これはシェイクスピアの翻訳で著名な福田恒存の『私の幸福論』の一部です。ほんとうは、万葉集後期の代表的歌人、大伴家持(おおとものやかもち、念のため)について、明治・大正・昭和の歌人、土屋文明があれやこれやとケチをつけているのが、まえから、良くも悪くも印象的でいつも気にかけているので、いまどきは桜の季節でもあり、家持の歌は、土屋文明さんに言わせれば、まあ、例えば人麿や赤人や、あるいは父、大伴旅人の歌のような量感に欠ける、ということは、歌が詠めないぼくにもわかる、でもね、ということを書いてみようか。これがこの雑文の主旨になる予定なんです。のっけからその主旨と直接関係なさそうな福田恒存の宿命論を引き合いに出したのにはいろいろ理由がありますが、そのへんはちょっと後回しにいたしまして、本筋の大伴家持と土屋文明について以下、予定を遂行してみましょうか。
土屋文明は大伴家持の平明な歌を一首、ほめたついでに、家持の歌一般について、どちらかというと否定的な見解を披露しているんですが、このくだりはちょっと気になります。
「堕落時代」って、ちょっと過小評価しすぎじゃないの、とかね、このことばはなんかの拍子にいちいち思い出されて、気にしたあげく、にやにやするんですが、土屋文明さんは、上の引用文の中の言葉で言えば「とどこおりのない」ということを重要に考えているのだということははっきりしている。家持の歌は全般に言葉の粉飾が多すぎる、と言いたいのだろう。だから、玉くしげ二上山に鳴く鳥の声の恋しき時は来にけり 大伴家持 家持は万葉集の時代としては、最後の人なので、彼の前には長い間の歌の業績が積み上げられている。それらはいろいろの点から家持の歌に働きかけるので、家持の歌にはそういう重荷に堪えかねたようなところがある。それがため家持の歌の数は多いのに優れた作は割合に少く、家持の歌というと、万葉集の堕落時代を代表するかの如く思われるのであるが、家持の歌にもこういう簡単で、とどこおりのない歌もあるのである。
というような広い意味の、天然のエロティシズムを謳歌する態度と、同じく女を歌っても、
みたいな、技巧重視、外面の効果、よく言えば視覚的なイメージの訴え方とでは、元手のかけ方が違うし、気持に訴える繊細さの点でも前者が勝り、後者は次元が及ばない、というようなことはなるほど言われればそうだろう。そうでしょう、この「春の園」の歌みたいな、印刷の視覚効果がくっきりしてるから気持のいいグラビアのような歌は、内容の面から見れば言葉の技術を愚弄している、浪費している、本末転倒であるというようなことだったら、おおもとでわたくしも賛成だ。でも、オーディオの世界で言えば、なにがなんでもハイ・ファイを追求するたぐいのこの種の態度や技術を、有害無益だと一蹴しきれるもんでもないよ。大伴家持が提示する視覚的なイメージはどれも、べつに変態ではない。むしろ逆だ。常識的過ぎますよ。桃の花の下に美女が立っている、風雅である、なんて、売らん哉の観光絵葉書じゃあるまいし、そりゃテレビも印刷もない奈良平安の御世にはいっとき新鮮だったかもしれないが、今日的に考えても別にどうと言うことはない、もっと粘っこく突っ込んだ情感を求めたくなる。が、観光絵葉書にトップレスの水着美女が写ってりゃ、おっと思って記念に1枚買って帰る好奇心、いいじゃないですか、そのくらい。そんなことも許さないのがインターネット・コミュニケーションの現状で、ここに実例として、ぼくがオーストラリアの空港(シドニー)で買い求めたパンティ1枚の美女の観光絵葉書をお見せできないのは残念ですが、えーと、さっきの大伴家持の「春の園」の歌の桃の下の女の人ね、ちっとも色っぽくないじゃないか。さすがに人麻呂さんは見るところはしっかり見ていると思います。詩歌で第一に重大なのは自然を詳細に観察し、自分の感動を取り逃がさないことである。土屋文明のようにそれが出来る本職の歌人は、以上に述べたように、時代を超えて大伴家持に苦言を呈しておりまして、大伴家持が自然観察に不熱心だったかどうだか知らないが、行き届いていないことは多々ある。こういう話のたどり方でもって、言語表現一般の永続性というものは、予測のつくこともあるように思うのですが、いかがでしょう。
という次第で紙数が尽きてしまいました。福田恒存の宿命論については機会を改めてお話しましょう。
問題 次の数式について、無難な解答をA−Fの中からひとつ選び、ぬりつぶしなさい。
1+2=4
B.この問題用紙はどうみても字がきたなすぎる。 C.4は2ではなく、2は1ではない。したがって、4は1+2になって、なにが悪い。 D.数字をいくら足しても、腹の足しにならない(または、なるわけがない)。 E.スージーちゃんなら、3万年もむかしに、終わったんだよ。 F.上の数式の正しい読み方は「ひーじゅーじー、日本しー」で、 わが国では太古から焼肉がさかんだったことが裏付けることが、すでに 「魏志倭人伝」をよめばわかる。 出題教官 多田乙山 2005年4月18日(月) 月末までに解答を提出しなければ、うちの長芋でぽこっと一発くれられれば、 すこしはきくだろう。 |
太鼓堂ウェブサイトを主宰して3年経ったら、けっこう膨大なページ数になりました。んで、いまさらのように気付いたのは、ウェブサイトというものを雑誌やテレビの概念で作っちゃいかんということ。意外な覚醒でした。「太鼓堂」の場合、トップページにフレームを使わないで、付け足し式に画像や文字を並べてリンクを張ってあります。視覚的にはこのほうが楽しいですが、来訪者の皆さんには使いにくかったかもしれないな。そんな考えから、このページのいちばん下にあるように、コンテンツ一覧というものを主なページ(全部に必要かどうかは検討中です)に設けることにしました。まだ改装中ですが、ひとまず、一番新しく更新したこの雑談ページからは、どこへでも飛んでいけるように、リンクを張ることにしました。「ウェブ上のコンサート」などいくつかは、技術的にトップページから動かせませんが、ご海容ください。出来る範囲であたりまえのことを補ったまでですが、どうぞこれを機会に好きなところへ飛んでってください。
東京の築地などでいまも引き継がれている歌舞伎という芸能がある。立派なものだとは思うが、どうも苦手だ。「江戸の娯楽」というところに由来する気取りが鼻について打ち解けない。首都を代表する芸能のひとつだということが念頭にあるから、これに親しめない自分のあたまがおかしいんじゃないか。そんな気にさえなる。だが、日本の文化を考えるとき、「中央」と「地方」とのあいだには今もなお、むつかしい断層が横たわっていると思う。これについて何か書いてみたい。とは言っても、「中央」と「地方」の境界線をどこに引っ張ればいいかというような込み入った話をするには材料不足で、単に好みを陳列するだけで終わっちゃうかもしれない。
能だったらよろこんで観にいく。強く土着性を感じる。一曲の能の舞台は、多く実在の地方の物語ということになっている。実際の演能ではその文学的な筋書の枠を超えて、どこかわからない高さから何者かわからない誰かが舞い降りてくる。ぼくが一回だけ目撃した故・観世銕之丞(静雪)の能舞台は、その象徴表現の中に観客の現実を定位させるという神業だった。ところが、この銕之丞さんが亡くなる直前(2000年)に出版した『ようこそ、能の世界へ』という本の中には「能はミュージカルのようなもの」と書いてある。能舞台がよくわからなければ、きれいな衣装を眺めていてもいいのです、音楽を楽しんでもいいのです、と言っている。能が「ドラマ」であることにもかなりの紙数を割いてある。たしか金春信高が、能はストーリーを楽しむ「ドラマ」ではなく、「詩劇」である、ということをどこかに書いていた。ドナルド・キーンも、「能の台本を詩として読み直せ」と言っている。能のドラマ性を強調した観世銕之丞は、『俊寛』を演じながら、いつの間にか観客までもがそのドラマの登場人物として舞台空間に乗り出している…ような気分にさせてしまった。
 能は卑俗な猿楽から徐々に発達したものである。それが室町時代に世阿弥の手によってひとつの芸能の型に高められ、これを足利尊氏が保護し、プロデュースしたことで大衆化した。ときの都は京都。奈良・興福寺では野外上演が催され、数千人の観客が詰め掛けた。言い伝えを信じれば世阿弥という人は美男子だったから、能というものは、美しい男に観衆がうっとりするようなショーだったのでしょう。ここらへんがうらやましい。
能は卑俗な猿楽から徐々に発達したものである。それが室町時代に世阿弥の手によってひとつの芸能の型に高められ、これを足利尊氏が保護し、プロデュースしたことで大衆化した。ときの都は京都。奈良・興福寺では野外上演が催され、数千人の観客が詰め掛けた。言い伝えを信じれば世阿弥という人は美男子だったから、能というものは、美しい男に観衆がうっとりするようなショーだったのでしょう。ここらへんがうらやましい。
歌舞伎の派手さは、きらびやかとか言う前にこけおどしで、外面の効果がおもしろいが遠近法がないと思う。ひとむかし前の名人がいなくなった、以前はこんなもんじゃなかった、という批評はよく聞くが、ことは名人の芸のありようの問題ではなくて、芸能そのものの立脚の問題だろう。江戸時代でも、地方の古典芸能には奥行きがあって、わけのわからないことでも古びのついた頓珍漢なよさがある。近世、近代以降になると、都会の芸能はばっと人の目を奪うビットマップイメージのようなものに変貌してしまう。1960年代、テレビが普及し始めたころ、寄席の芸人、落語家や漫才師のなかで、あくまで寄席にこだわった人たちは廃れ、テレビというニューメディアでも活動をはじめた人たちは長持ちした。しかし、だからといって寄席が次々につぶれなくてもよかったはずだ。こういうところに「中央」と「地方」の違いが見えてこないか。
伝承や伝統、「過去」とばかり付き合っているのは肩がこる。でも、ビットマップイメージだけ増えていったら、いずれ順列組み合わせも尽きてくるし、次々と新種のネタで散らかるし、モノの集積が意味のわからない街の相貌になったんじゃ、なにやったって埋もれてしまう。芸能の奥行きは非合理なもの、勘定の合わないものを多く含んでいる。だから内容の吟味検討も出来れば、先々の進路を占う素材にもなってくる。ぼくだったらそういう楽しみ方で話を持って行きたい。と思います。
本日はちっとも晴天でなく、うっとうしい曇り空で、散歩に向かない気候である。だから、この拙文は散歩代わり、気晴らしに書いているので、学術的な信憑性は皆無だし、世のため人のために何か寄与することがたとえあったとしても、そんなことをもくろんで書いているんじゃなくて、単に、自分の主観、目下の関心について言えそうなことを言ってみるだけの文章です。こういう内容を著述するときには、「自分は今、虫のいどころが悪いです」とすなおに白状したほうがよろしい。これはノーベル物理学賞の朝永振一郎博士や、数学の森毅教授が採用している方便に倣ったのです。こういうマナーも必要だと思いました。
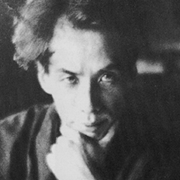
これは、先般この雑文にご登場願った福田恒存さんによる、芥川龍之介批評です。芥川は自己肯定を行うために、文学を比喩として取り扱った、ということです。この批評は芥川龍之介の作品に対しても人格に対しても最大限好意的である。芥川の文学および人となりについて、芥川に成り代わって行いえた、ひとつの重大な問題提起でもある。もうひとつ、最近になって出た興味深い芥川批評。
芥川の文章は一語一句をゆるがせにしない潔癖症があり、みがきぬかれた文体はきしみあいスックと立ちあがっている。しかし、理知的がゆえにダシがきいていない。
嵐山光三郎『文人悪食』(新潮文庫)より
このふたつの批評が共通して指摘しているのは「主体の欠如」ということである。芥川龍之介が自分の感じたことやものの考え方を直接、小説に仕立てることを嫌い、日本の古典文学を枠組みとして借用することで作者の日常を隠蔽あるいは抹消し、現実と直接接触していない物語の世界を構築した。一般に、これは「私小説の否定」という、20世紀の日本の文学界で大問題になった創作態度であるということになっている。たとえば恋愛小説を書くときに作家が実験恋愛をしてみて、その体験をありのまま書いたものなどが私小説と呼ばれた。そのへんの事情をじっくり研究した著作に、伊藤整の『近代日本人の発想の諸形式』という名著がありますが、そうねえ、やっぱりこういう冷静沈着な判断を残酷で冷たい知性といって敬遠するひとは多いのでしょう。ぼくはこの本が好きでさんざん読んだのに、10年経ったら何書いてあったかすっかり忘れてしまった。ただ、島崎藤村が告白小説『新生』を発表したとき、田山花袋が「島崎君は自殺する」と言って立ち上がったのに対し、芥川龍之介が「藤村のような偽善者はいない」と書いた、というくだりは強烈だったのでしばしば思い出します。引用したいところだが長すぎるので、興味をお持ちになった方はこの本の16−17ページをお読みください。岩波文庫です。
 このことと、旧ソ連の作曲家、セルゲイ・プロコフィエフと、いったい何の関係があるのか。いちおう「主体」つながりということは申しておきましょう。んでさ、ここに彼の代表作として『ピアノソナタ第6番《戦争》』を挙げる主要な理由は、ぼくが小学5年のときにこの曲を聴いて興奮し、20世紀音楽への嗜好の中心にこの曲があった、という個人的な事情だが、ぼくが興奮したこの曲の演奏はデビュー当時のヴラディーミル・フェルツマンによる、モスクワ音楽院ライヴの実況録音(NHK・FM)だった。フェルツマンというひとは日本ではほとんど知られていないが、きわめて本質的な技巧家であると同時に、抜きん出た解釈者である。まったく、猛烈なプロコフィエフで、プロコフィエフ本人だってこんなに過激には弾かなかっただろう。過剰な解釈と言えばそれまでだが、周知のとおり、プロコフィエフを「過剰に」解釈して演奏としても成り立っているというのは至難の業で、そのことは、プロコフィエフと親交のあったスヴャトスラフ・リヒテルが演奏する同じ作品を聴けばよくわかる。リヒテルはこの曲が好きで、ほぼ一生のあいだ弾き続けたが、どの演奏記録を聴いても、いわゆる「技術的に」まとまったものなどひとつもない。リヒテルが下手だ、などといっているのではなく、リヒテルには下手うまいの尺度がないかのようだ。それは、言ってみれば壊れたところのある作曲家像を差し出すのであって、創造は破壊であるというような、芸術家が本来いいたいが、自分では弾けないことを、当人に成り代わって弾いている。リヒテルの演奏はそこまで見通した結果である。プロコフィエフのピアノ曲には、「壊してしまえ、壊してしまえ」と意味を叩きつけた挙句、せっかくガンチクのある音もトレーラートラックでひき潰したようなところがあり、これだけ、ある意味で一面的に直撃してくる音を書いた作曲家はそう多くない。フェルツマンの演奏には、この一面性がよく出ている。味噌もくそもない、ではなくて、なんだろう、「情け容赦ない」音だ。…ということになれば、これは日本文壇における私小説の世界と似たところがある、のじゃなかろうかと、はっと思ったんですよ。(こじつけすぎかなあ。こじつけでもいいや。)それが、ソヴィエト共産主義に対抗する彼なりの手管だった、とでも考えないと、正直なところ、ばかばかしくてやっていられないような楽想の展開が随所にある。プロコフィエフはちっとも懐疑しなかった。思うことを思うように組み立てた。この『ピアノソナタ第6番』は、旧ソのプラウダ誌から形式主義と糾弾され、プロコフィエフは形式主義という共産主義の用語を「いちど聴いただけでは理解できない音楽に与えられる呼称」と定義している。だから、ダシは充分にきいている音楽だ、ききすぎか、などと話を誤魔化して、この拙文の結びといたします。
このことと、旧ソ連の作曲家、セルゲイ・プロコフィエフと、いったい何の関係があるのか。いちおう「主体」つながりということは申しておきましょう。んでさ、ここに彼の代表作として『ピアノソナタ第6番《戦争》』を挙げる主要な理由は、ぼくが小学5年のときにこの曲を聴いて興奮し、20世紀音楽への嗜好の中心にこの曲があった、という個人的な事情だが、ぼくが興奮したこの曲の演奏はデビュー当時のヴラディーミル・フェルツマンによる、モスクワ音楽院ライヴの実況録音(NHK・FM)だった。フェルツマンというひとは日本ではほとんど知られていないが、きわめて本質的な技巧家であると同時に、抜きん出た解釈者である。まったく、猛烈なプロコフィエフで、プロコフィエフ本人だってこんなに過激には弾かなかっただろう。過剰な解釈と言えばそれまでだが、周知のとおり、プロコフィエフを「過剰に」解釈して演奏としても成り立っているというのは至難の業で、そのことは、プロコフィエフと親交のあったスヴャトスラフ・リヒテルが演奏する同じ作品を聴けばよくわかる。リヒテルはこの曲が好きで、ほぼ一生のあいだ弾き続けたが、どの演奏記録を聴いても、いわゆる「技術的に」まとまったものなどひとつもない。リヒテルが下手だ、などといっているのではなく、リヒテルには下手うまいの尺度がないかのようだ。それは、言ってみれば壊れたところのある作曲家像を差し出すのであって、創造は破壊であるというような、芸術家が本来いいたいが、自分では弾けないことを、当人に成り代わって弾いている。リヒテルの演奏はそこまで見通した結果である。プロコフィエフのピアノ曲には、「壊してしまえ、壊してしまえ」と意味を叩きつけた挙句、せっかくガンチクのある音もトレーラートラックでひき潰したようなところがあり、これだけ、ある意味で一面的に直撃してくる音を書いた作曲家はそう多くない。フェルツマンの演奏には、この一面性がよく出ている。味噌もくそもない、ではなくて、なんだろう、「情け容赦ない」音だ。…ということになれば、これは日本文壇における私小説の世界と似たところがある、のじゃなかろうかと、はっと思ったんですよ。(こじつけすぎかなあ。こじつけでもいいや。)それが、ソヴィエト共産主義に対抗する彼なりの手管だった、とでも考えないと、正直なところ、ばかばかしくてやっていられないような楽想の展開が随所にある。プロコフィエフはちっとも懐疑しなかった。思うことを思うように組み立てた。この『ピアノソナタ第6番』は、旧ソのプラウダ誌から形式主義と糾弾され、プロコフィエフは形式主義という共産主義の用語を「いちど聴いただけでは理解できない音楽に与えられる呼称」と定義している。だから、ダシは充分にきいている音楽だ、ききすぎか、などと話を誤魔化して、この拙文の結びといたします。
ある日、よく晴れた朝、女の子がね、この国に君臨している、醜い顔をした王様を征伐しようと、剣を持って旅に出た。ここまではよかったんですよ。なにしろ、国政が乱れているのに、王様は、あろうことか、釣りゲームと挟み将棋に興じてばかりいて、国中の女子供が悲嘆にくれるなか、大新聞社がパブロ・ピカソの『泣く女』という絵を、ジョークでしたが、まいっかーと社長が、ユーモアのつもりかなにか知らんが、政治面をまるごと使って報道したというのに、王様は、情けがうつって、感極まって泣くし、ろくなことになってません。でも王様は、残念ながら、お后様にうだつがあがらなかった。なぜかというと、王様はだらしがなかったからである。なぜだらしがなかったかというと、誰も知りませんでした。女の子は、むつかしい国政のことがよくわからなかったので、新聞がよく読めず、よくわからなかったので、王様とお后様が、夫婦だということがよくわかりませんでした。レオナルド・ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』が王様のお后様だと、本気で信じてい、大新聞社は、こりゃあ、わが社がいくら儲かっても、と途中までしか言わないうちに、泣けてくるし、王様は、釣りも将棋も負けてばかりい、理解に苦しんでいました。女の子のせっかくの剣は、あまりに長い征伐の道中、雨風にさらされて錆び、くしゃっと折れてしまいました。おなかがすいたので、ドライヴ・インで休憩しています。注文したビーフカレーは、いかったが辛え。偶然、王様も、同じ時刻に、お后様と、チキンカレーを召し上がっていたのです。それはね、女の子がね、王様征伐に出かけてから295日目の、よく晴れた昼の飯でした。女の子はね、ビーフカレーが辛かったので、王様征伐のことはすっかり忘れました。うちへ帰ったらブランコに乗ろう、と思いながら、もと来た田舎道を引き返す途上、うっかり、どぶにはまって、脛とおしりにケガしました。[終]
《問題》 犯人はだれでしょう。1.女の子 2.王様 3.パブロ・ピカソ 4.大新聞社の社長
4.お后様 5.ドライヴ・インの板さん 6.レオナルド・ダ・ヴィンチ
《教訓》 国破れて山河あり 城春にして草木深し
風呂場の壁がみんな透明なガラスだったら、助平のひとたちは喜ぶだろうが、花恥らう娘さんたちはおちついて入浴できないはずである。はずであるって、まあ、例外もいらっしゃたりしますし、状況しだいではおもしろそうな趣向になることもあり、いや、この発想はぼくがヒマだから出てきたわけじゃなくて、明治初頭に、女湯と男湯の境をガラスで仕切った銭湯が実際にあったそうだから、いつでもこういうことでひとはにやにやしている。ただし、この銭湯のおやじさん独自の発案で、仕切りのガラスの女湯のほうには歌舞伎の役者を描き、男湯のほうには芸者を描いて、両方の浴室がもろに見えないように工夫を施し、開業の当日まで、おやじさんは自分の発案に得々としていた。ところが、いざ店を開いたら、浴槽の湯気がモウモウとたちこめ、せっかくのガラスも役者絵も芸者絵も全然見えなくなっちまった、というお話。
この話でさっぱりわからんのが、女湯のほうに役者を描いて、男湯のほうに芸者を描いて、というアイデアだ。だってさあ、いまの時代で似た話を想定すると、大衆浴場(大衆欲情、なんて、くだらんしゃれはうんざりかもしれませんが、我慢してください)の女湯に木村拓也の、ヌードってわけにもいかないだろうからなんかかっこいい大写真を飾って、男湯には黒木瞳の、やっぱり、いくら映画やテレビのセックスシンボルだって、全裸はいかんでしょうから、にっこりえくぼがすてきな等身大写真を掲載しております、レジャーにぜひどうぞ、なんて言われて、お金払って入浴しに行きますかね。言われたとたんに興醒めじゃないでしょうか。行かないと思うねえ。実物がおります、っていう触れ込みなら百万人が殺到するかもしれない(そういう大浴場は、世界中探せばひとつぐらいあるでしょう)。しかし、着衣のキムタクくんや黒木瞳おねえさんの前で、百万の一般大衆が脱衣入浴するんですか。しないでしょうよ。それに、木村さんや黒木さんは仕事で大衆浴場に現れるんだから、どんな過酷な状況にも耐える職業意識が、とか言ったって、これは「主客転倒」(なんか違っているような気がするけど)というやつではないだろうか。木村さんや黒木さんと一緒にお風呂に入ろう!というツアーなら、話はわかる。話はわかるが、いや、駄目だ、わかるような気がするだけだ。木村拓也くんが男湯に入り、黒木瞳さんが女湯に入る。あたりまえだ。銭湯の壁の考察なんか不必要ではないか。この拙稿が愚考にならないためには(なんでこんなところで頑張っているのか問われても、ただ考えてみているだけですよ)、ぜひとも、男湯に黒木瞳が、女湯に木村拓也が入ってくれないと都合が悪いです。これは話を拡大しているんです。実際には、男湯と女湯の境にガラス板が立っていて、男湯の側面に黒木瞳さんの等身大の美女大写真が、女湯の側面には木村拓也くんの美男子大写しがかかっているだけである。これが、この銭湯の営利にどのくらい影響するかという話をしているんです。高が知れているような気がしますね。この趣向で儲けようと企てるならば、いっそ特別企画にしたらどうでしょうか。写真じゃなくて蝋人形を、10体ぐらいつくり、ヨコ一列に並べて男湯と女湯を部分的に遮断する(実際を想像してみましょう)とか、写真だったら木村さんや黒木さんの百面相をいっぱい貼る(これも、想像してみよう)とかする、というように。現代アートの応用でこういう思いつきが可能なかわり、理解困難な銭湯になる可能性が大きくなるから、営業利益の期待値は減少する。百万人なんて来ない。1000人ぐらいは大丈夫かもしれない。しかし、たった1000人では営利どころか、大赤字じゃないか。理論的に経費をおさえて黒字にしようと思ったら、やはり、実物と一緒に入浴ツアーがいちばん確からしい。実物といったって、歌手や俳優だから成り立つ話なので、これが専門のAV男優やAV女優だったりなんかしたら、そもそもここは銭湯ではない。目的がずれて
ここまで書いてはっと気がついたんですが、こういう筋の運びにのっとれば、最初に書いた明治の銭湯、あれは、実物の役者や芸者でなく、役者絵と芸者絵というところ、「絵」というところがミソなのだ。ここにホンモノの歌舞伎役者やら芸者ガールやらを出してきたらぶち壊しだろう。銭湯と歌舞伎座、楼閣を足して3で割らなければならないではないか。そんなめちゃくちゃなこと、漫画にもならない。宣伝だから、流行の風俗のイメージだから、客寄せになる。ガラスなんかに描いちゃったら、ハイカラだしきっとウケるぞ。おやじさんはその程度、考えていた。だから、感覚的にはむしろ現代アートみたいなものであって、街の商いとしては、百万人なんか期待しなかったはずだから、近所の商売で成り立ったんですよ。ちがいますか。明治時代の特異な文筆家、斉藤緑雨の鋭い観察は、そのポンチ絵的なおおらかさ、別に言えば間抜けさ加減がおもしろい、語るに足るとみて、ひとつのゴシップに仕立てた。その結果、明治のガラス張り銭湯なんてものが後世の語り草になっていて、なんとなく心が和むなあ。名文の力、と言わずに、これをなんと言うのだろうか。お待たせしました、斉藤緑雨さん、ご登場ください。
女湯には俳優 、男湯には藝妓 の似顔を玻璃 に摺りて、背中合せに雙方の仕切としたる湯屋の亭主の、ここが陰陽の妙と得々たりしが、開業の當日より湯気立罩めて、霞の中の花とも云はれず、折角の大意匠も水船の泡と消えぬ。
専門の文士にはこういう芸が可能なのだ。壁の考察なんかどうだっていいから、どなたか、憧れのスターと一緒にお風呂に入ろう!という企画を、是非、考えてくださらぬだろうか。少しは国益に利するところありとみているんですが…。

(この画像にリンクを張っておきます。
お友達や彼氏彼女を誘って鎌倉へお出かけください。)
専門の文章家に言わせると、欠点のない長編小説はないのだそうである。ぼくは小説が書けないし(あんな途方もなく膨大な労力を言語につぎ込まなければならない小説家という職業に脱帽します)、読むのは好きというだけで、外野から無責任に感想を言うのがせいぜいだ。そのあたりで言うと、フレデリック・フォーサイスというイギリスの小説家の長編『第四の核』を読んだとき、ひとりのスパイを調査して半世紀も時間を遡行し、現在へ戻ってくるまでに作品全体の4分の1を費やして、この部分を読んでいるあいだはなにやらいつまでたっても要領を得ない話に見えたのが、通過した時点であっと息を呑んだ。こういう筋の追い方でこの部分はちょっと長いぞと感じさせるのは、欠点なのかどうか。どうでもいい話のようですが、作者は食い下がって克明に書いたのだから、ここは圧巻でおもしろく、あそこは冗長でムダがあり、などと簡単には切り分けられない。
唐十郎が状況劇場という劇団を主宰していたときの作品に『あるタップダンサーの物語』がある。2時間半ぐらいかかる芝居で、新宿・花園神社に赤いテントを張り(だからこの劇団のニックネームが「赤テント」)、たぶん100人以上の観客がござ席にすし詰めになっていた。元号が平成になる何年か前で、人形作家、四谷シモンがあでやかな女形で登場してみものだった(現在の佐野史郎がこのときの公演に出演していたことをあとで知った)。とにかく唐十郎と状況劇場の演劇は筋の運びが速いのか、なにか意識的に邪魔を入れているのか、観ている途中から意味がわからなくなるのが毎回の特徴で、わからなくなるだけではない、何しろ環境が、赤テントのござ席にすし詰めで動けないから脚はしびれるし、尻は痛いしで、演劇が終わるまで、頭も体も引っ掻き回されて、おもしろかったけどとんでもない体験でした。こういうのは長いというのかな。芝居の筋がアタマのなかで混乱する、座りずくめで脚が痛くなるからときどき体勢に気をつかわなければならない、ということを往復しているうちに、自分はいまどういう体験をしているのかわけのわからない心境になったり、させられたり、あれは明らかに意識的に、主宰者が観客をそういう環境や心境に誘い込む作戦だったはずだ。この長さ。
ショスタコーヴィッチという旧ソ連の大作曲家は交響曲を15曲書いた。有名な第5番『革命』は30歳のときの作品で、50分を非常に簡潔に無駄なく処理した筆力は並大抵でないが、これは旧ソヴィエト共産党の機関紙「プラウダ」紙上での批判に半ばへつらった結果ではないかと意地悪く見る人がいる。この曲のひとつまえの『第4交響曲』が、やはり1時間近くかかる曲だが、一体なにが言いたいんだか構成も和音も支離滅裂なところがあり、独り言をいつまでも続けているかと思うと矢庭に陳腐な感じのする行進曲になったり、突如爆発したりで、そのへんの徹底的なアンバランスが、作者にはどうだったかはともかく、聴いているぼくには明らかに一種のおもしろさなのだ。かなり長さを感じさせる作品には違いないが、これだけ乱れているのもあまり例がないという興味を抱くのである。断るまでもなく、作者には気の毒な鑑賞の仕方です。ショスタコーヴィッチはこの曲のリハーサルの最中に楽譜を撤収して帰ってしまったという史実があるからだ。なにか、作品の構成上、ひどくまとまらないことを気にしていたのは事実だと思う。それが旧ソ連政府のプロパガンダとどういう関係にあるか、ショスタコーヴィッチが自伝でどう言おうと、だれのどんな説明も憶測の域を出ない。ただこの曲には、その破調のきたし方に独特の世界と魅力がある。
少なくともCDで聴く限り、フィリップ・グラスのオペラ『浜辺のアインシュタイン』は全曲を通して体験するには骨が折れる。いくらミニマルオペラといったって、CD3枚も同じことの繰り返しはもういいじゃないか、のような気分になりがちだ。だから、この作品は劇場で観てみたい。まだ観たことがない。2年前に公開された、ニコール・キッドマン主演の『めぐり会う時間たち』という映画(原題は「The Hours」)の音楽担当がこのフィリップ・グラスだった。音楽はもちろん、映画じたいの構成もすばらしく刺激的で、あそこでは、グラスの音楽と、音楽以外の雑音・廃棄音のたぐいの衝突や混ざりあいが(どの程度意図したことかは知らないが)ある種の心地よい挑発となって語りかけていた。現時点でのグラスは、もうミニマル音楽の作曲家とは呼びにくい。しかし彼は現在、ミニマル音楽をやっていた頃よりもっと端的に、ある興味深い不条理を、たとえばひとつの和音で打ち出してくる。その、興味ある不条理を言おうとして3時間も音型の反復を続けていたかつてのグラスがいたのだから、『浜辺のアインシュタイン』の劇場版は、きっとCDよりもおもしろいのだろう。長くてかまわないからいちど観てみたいなあ。
ある長さの時間が経過すると、そのあとは退屈になったり、じりじりしたりということは日常、よく経験するが、それならそのぶんの時間をほかのことに使えばいいのかとか、例えばディズニーランドのアトラクションのまえで2時間も待つことや、初詣の人ごみでもみくちゃにされることは馬鹿みたいな空費なのかとか、実際そうなのかもしれないが一概にそうとも言えない、言い切れない時間がある。こういうことは人間のあらゆる行動につきものだといってもよい。それなのに、ぼくたちはしばしば、このたぐいの時間のすごし方におもしろくない思いをし、あるときには腹を立てる。なぜなんだろうか。うまい話はないとか、地獄を知って初めて天国を知るとか、ヒマだからこんなこと考えているんだとか、いくつか、どこかで誰かがたいてい言っている言葉はあるが、頭の隅に置いていていい疑問だという気がします。少なくとも、これを考えたからといって、日常生活や読書、音楽、演劇の邪魔になることもなさそうだし、逆に、かえって捗る可能性が想像されるのだが、いかがでしょうか。
蛇足ですが、味噌汁を作るのに夢中になることがある。コクのある薄味が好きで、自分でも凝りだしたが、ある種のマンネリズムに陥り、抜け出すには苦心するね。塩分の摂りすぎが血圧にわるいという健康雑誌の忠告は、ひところあちこちに見られたが、最近あまり言わないですね。具をたくさん入れれば済むことだったり、ダシを上手にとれば味噌の味付けはごく薄くてもおいしい。料理は下手だったが、やってるうちにどうにか食べられる惣菜ぐらいは作れるようになった。とはいえ、ダシのことになれば専門的には奥が深いだろう。自宅の厨房でダシの研究をやるほど熱心ではない。煮過ぎてドロドロになったけんちん汁のようなものがきらいなので、味噌汁ぐらい、自分の好みの味つけがいい。それと、具の選びがわるいとどうしようもないみたいですね。春菊とマイタケは、いいアイデアのようだが合わない。

コンサート終了後、決してサボっていたわけではないのです。しかしさすがに、梅雨入りからの中途半端な天気には参りました。平成7年に1回目の『江村夏樹ピアノ独奏』を開催して以来、10年が経過しました。太鼓堂の名前で主催したコンサートは16回。このさい、10年の節目だからというので、以前のコンサートの記録映像を整理していたのです。インターネットの歴史を振り返ると、個人がコンピュータを持つようになったのがだいたいここ10年前後、電子メールが民間に普及し始めてやっと5年です。メールのまえはファックスが主流で、それ以前はワープロ原稿か電話でした。新しいメディアが普及したからといってコミュニケーションの質まで変わることはないが、個人がCDやDVDを作れるようになったのは、便利というだけでなく、カセットテープやビデオテープとLPやレーザーディスクの時代には考えられられなかったような物質と情報の交換が可能になりました。メディアが変わったからといって、人間が偉くなることもない、コンピュータが個人に浸透したからといって、生活が夢のようにすばらしくなったわけもないかもしれない。ネット上のいやがらせは今後増えるだろうし、まだ不況は回復しないだろうし、イラク戦争が始まって4年経ったのにまだやっているし、だからといってうちのなかに理想郷を組み立てて篭城してばかりもいられないし。このサイトの歴史が4年なんですよ。改めて振り返ると、この10年、コンサートを主催してきたことは、回数は少ないながら、自分の成長と社会の動向との交点でいえそうなことをやってきたと思います。今後も継続しますが、ただいま、以前のコンサートの記録をCDやDVDにまとめております。これらは資料で、一般の商店には流通しませんが、いまではネット上でも情報が見当たらなくなったコンサート、それでなくても、そもそも地味な太鼓堂の興行の経過の一端を皆さんにお伝えできる告知が、夏休みあたり、このサイトに出ますので、ご期待ください。末筆ながら、過ごしにくい天候ですが、親切な読者のご健康をお祈り申し上げます。じゃあ、次回。
岡本太郎という日本の画家の油絵を見て思ったのは、「音がきこえない」というようなことだった。真っ赤な画面がしーんと静まり返っている。だが、正確に言うと音がきこえないのではない、何か異常な静寂がきこえてくるのだ。水琴窟や鍾乳洞をのぞき込むように、あの、原色ばかりの画面の奥へ連れ込まれていくような、ちょっとこわい思いがした。この画家がピアノを弾いたことはよく知られている。自宅でショパンの『軍隊ポロネーズ』を弾いている様子がテレビで放映されたし、NHKの「藤山一郎ショー」や民放のなにかのコマーシャルでぶっ叩きの即興演奏を披露したこともある。一種の騒音に近い響き、音楽としては作られていない音、まとまらず、しかし正体ははっきりつかむことができる演奏だった。音の塊の中に、粗いところと細かいところが聞き分けられるような粒子の分布が見えた。たぶんね、推測ですが、岡本太郎は絵の制作中、その絵と対応している現実の聴体験を、趣味の領域ではピアノの音に置き換えていた、その部分が、鑑賞者が実物の絵画作品に接した場合には「音がきこえない」という印象を引き起こすのじゃなかろうか。いろんなことの積み重なりが「音がきこえない」という結果を来たしている。そんな気がしました。こういう具合にくそまじめに話を進めることは別に美徳ではありませんで、ピアノ演奏は岡本太郎には絵画制作の景気づけ、気晴らしウサ晴らしでした、だから「なってない演奏」にすぎなかったとか、茶化すほうが、ぼくは好きですけど、ちょっと気取ってまじめぶってみましょう。
美術の分野でこの種の「ないこと」をぶっちゃけて話せば、例えばマルセル・デュシャンが、何を作ったってしょうがありませんと悟ったのかどうか知りませんが、やれマット社の便器ですとか、パリの空気の瓶詰めですとか、『モナ・リザ』の写真に鼻髭を描き加えただけで、『彼女のおしりは熱い』という題をつけたとか、こういう発想は特別の人物が特別に考えて出てくるというようなものではなくて、人間なら誰でも考えることである。たいていはバカバカしすぎるから実行しない。日本のどこかの食品会社の宣伝コピーの制作を担当した本職のコピーライターがさんざん考えたあげく、『おいしいですよ』←という作品を得た。当然これはボツになりました、という話を糸井重里が書いていた。こういうとぼけた話は好きだなあ。
よく引き合いに出される無音の代表が、ジョン・ケージの『4'33”』という音楽作品ですが、これだって、何を作ったってしょうがありませんと悟ったあげく、何も書かなかった、と言ってしまえば、話は終わってしまう。ぼくはケージが鹿爪らしく哲学した結果、この無音の作品が出てきたとは考えたくない。もうちょっと別の、ある特殊な思いつきなのだろう。そこら辺の事情はよくわかりませんが、この無音について、無音ならぬ実際の音で考えようとしたらしい人物がひとりいる。カナダのピアニスト、グレン・グールドである。[続く]
グールドがやろうとしたことは、他人の作を演奏で模倣することだった、彼は限りなく作品に近づくだけでなく、作品そのものになろうとした。ということなら、最終的には、ひとが作った曲とまったく同じ曲をグールドも作らなければならない。しかしそれは不可能なので、グールドは演奏行為と、演奏している作品とのあいだに美的エクスタシー、それも、確実な高揚感を求めた。だからコンサートを拒否した。グールドについてはいろんなことが言われているが、否定的な側面だけをとればたぶんそういう図式なんだろうな。だとするとずいぶんくだらないスリルを追い求めたピアニストだったということにしかならない。レコーディングスタジオの中でエクスタシーを体験しよう、創造しようといったって、グールドの場合、たいていはひとの曲をピアノで弾いていたわけだから、経験原則から推測して、いちばん創造行為が成り立ちにくいテクノロジーの中でならエクスタシーが体験できる、だからテクノロジー万歳なんて、ちょっと話が安っぽすぎやしませんか。音楽家といわず、人間にはこの種の妄想を無茶を犯して追求し続ける種族がいる(かく言う誰かも、まあそのひとりかもね。可能性は否定できない)。おそらくこれが、グールドの言う「対位法」の実態で、かれが「対位法」というとき、相手どることができる、かたちのあるものを追い求めていたに違いない。結局それはレコーディングスタジオそのものや、テクノロジーに囲まれてピアノに向かったときのグールド自身、彼の身体だった。プロの作曲家なら、いくらなんだってここで立ち止まり、少し考えるだろう。自分のやりたいことを考えなおしてみるはずだ。たとえば、ストラヴィンスキーだったら考えた。ジョン・ケージやシュトックハウゼンも考えていた。残念なことに、作曲家としてのグールドにはこの種の裁量がなかったようにみえる。ただ肝心なのは、そして厄介なのは、手段は変でも、このグールドの方向じたいには信憑性があるらしい、ということだ。従来の批評はこの区別を見落としていないだろうか。グールドの営みを見ていると、自分がこうだと決めつけたバッハならバッハは楽譜という形をしたガクブチに過ぎない。そこから入ってどこまでも奥へ歩いていったら何が見えるか、ああだこうだといろんなアクセサリーを試みたあげく、ついに形が見えてこなかった。そこに自分の成り立ちを確認する冷静な判断が働かなかった。来たるべき形が見えないまま彼は死んだ。こんなことをいっていたら、グールドの業績は台無しになってしまう。ピアニストとして、既成の古典音楽のガクブチを楽譜どおりにただなぞっていただけでしたということになる。まさか、彼のそんな幼稚なつまづきに、今まで誰も気づかなかったわけがないし、グールドその人も、この演奏行為の罠に気づいていなかったはずはない。ジョン・ケージとおなじように、グールドも、シェーンベルクの無調音楽に啓発され、独自にその行き着くところを模索した結果、古典音楽をピアノで弾きながら全然別のことを妄想するというような二束の草鞋が履けないことに、彼は死ぬまで反発していた。その執着はおどろくべきもので、彼のスクリャービン演奏に聴かれ、見られるような「エクスタシー」は、たとえそれがナルシスティックでばかげた妥協の産物だったにせよ、というより、そういう妥協の産物だったからこそ、現在でも生きながらえて、衆人環視に耐え、後代の音楽家や音楽ファンに、音楽のやり方にはこういう手段もあるんだぞというモデルを提供している。それは何かの錯誤である。しかし、音楽のプロや愛好家がこの錯誤に何らかの処方や言い逃れを講じる必要があったことは、なにも現代特有の問題ではない。時代によって形を変えて繰り返し現れる音楽の問題ならば、もうそれは、どうでもいいことではなくなった。[続く]
話が堅苦しいから画像を載せておきます。リンクを張ってありますので、遊びに飛んでってください。
 |

|
ご無沙汰しました。夏風邪で寝込んでました。治ってきたので話を続けましょう。
空白についてあれこれ広げ散らかそうとしていた文章の矛先が、グレン・グールドのワルクチになっちゃったところでちょん切れていたのでした。そこへ、ぼくが夏風邪とバテで寝込んだから、空白の話をやってる最中に、このウェブサイトの更新まで空白になりました。まあ、しかたがない。もうちょっとグールドについて雑談してみよう。
ピアニスト、グールドの基本の演奏マナーは拍が正確なことである。ほかの大多数の演奏家と違って、グールドの拍のとりかたは、定規で測って均等に割るとか、メトロノームに従属するとかいうような類で、なにか、四角い箱を組み立てているような印象を受ける。その四角い箱の材料が、古典ピアノ曲の記譜だった。1960年代、ステージでのコンサートをドロップアウトしたばかりのころには、グールドのレコーディングのあるものは非常に雄弁で、ちょっと反則じゃないのかと思うぐらい、原曲を置き去りにして自分のパフォーマンスを優先している。これとは反対に、コンサートに出演していたころのライヴ音源には、のちにスタジオ録音に専念するようになった時期の演奏とくらべ、まるで元気がないものがある。ザルツブルグのコンサートの実況などはその端的な例だが、コンサートを始めた20代の記録にはもっと勢いのあるものが知られていて、モスクワ音楽院で学生を相手に披露した解説つきのコンサートに聴かれるベルク、ウェーベルン、クルシェネック、バッハの演奏は、後のスタジオ録音を上回る奔放な表出が、どうやらヨーロッパの伝統を踏み越えて過剰に聞こえるところがあり、そこにグールドの独自性も正当性も発揮されているというような演奏である。ステージ上でかしこまったときのグールドは、記録音源で観察する限り、こういう自由を根こそぎ奪われてしまう。グールドのレコーディングのなかで、彼のよさが非常に発揮されているのは、たとえばベートーヴェンの作品10のピアノソナタ3曲である。録音コンディションとか気分とかがかもし出した偶発的な成果なのかもしれないが、暴力すれすれの挑発と、やさしすぎるくらいの叙情性が同居している。レコーディング演奏家としてのグールドのしごとは、この先、「古典作品の演奏での創造性」という宿題に向けられていたはずだったと思う。これは、ヨーロッパ音楽の伝統という厄介な問題にそのまま置き換えることができるほど、一人の演奏家が背負い込んだ宿題としては大きなものである。別に、スタジオに閉じこもらなくたって、グールドの主要主題はステージ上でも同じだった。演奏における創造性という主題は、スタジオの中のグールドの自発性・自律性をかえって弱めてしまった。これは、よく言われているような、コンサートだったらこの種のマンネリズムに陥らなかったはずだ、グールドの選択は誤っていた、という種類の問題とは違う。グールドが抱え込んだのは造形の問題で、造形の問題は外からやってくるのではなく、一人の演奏家の自発性や自律性から出発する。内側から突き上げてくる欲求が、結果としてある形になる、という順序は、ヨーロッパの音楽伝統の中ではたいがい、倒立しているか、馬鹿げているとみなされる歴史がある。こういう伝統のとらえかたはヨーロッパに限らず、どこの地域の音楽でも、意固地なこだわりじゃなかろうか。本質的に、創作や創造は伝統を踏み越えるものでなければならない。そして新しい創作や創造は、それ以前の歴史の積み重ねを踏まえていなければ成り立たない。このふたつのことは、両立はしないかもしれないが、べつに矛盾していない。求められているのは過去との対話、それも、ひとりひとりが、能力の有無に関係なく試してみたほうがよい対話である。じつは、これにはコツがいる。そのひとなりのやりかたがあるが、対話の性質として、べつに音楽的なことがらでなくていいわけで、というか、対話していけば音楽から焦点がそれていくはずみがあるし、音楽のためにもそのほうがよく、べつに結果を音楽にぜんぶ還元しなくたっていいはずなのだ。こういう経緯をたどると、あるところで音楽が見えなくなる場合がある。ある種の危機には違いないのだが、音楽が見えなくなったって、ほかのものは見えている(なにが見えてるんすかー)。かえってそういうことがないと以前からの音楽も継続発展していかないのだ。誰かが、何かが音楽をしっかり支えているから、みんな好きにしていいよなどというという保証つきの無法地帯に先の見込みが成り立つわけがない。信頼するに足るもの、嗜好の対象、精神的帰郷はなにも音楽でなくてもいいし、どこから出発したって、歩いていけばA地点からB地点に移動するか、B地点からA地点に移動するか、B地点からC地点に移動するのである。晩年のグールドは、バッハの『ゴルトベルク変奏曲』の2度目の録音を、やせた音と強迫的なパルスで完璧に仕上げた一方で、ブラームスの『ふたつの狂詩曲』では、なにかが破けてしまい、猛獣のように牙をむきだした。にもかかわらず、どちらも、独自の解釈と技術と魅力が尊重されている。これらは、今日の音楽伝統と信じられているものの図解ではないだろうか。
ここから、次のページへ飛んでください。
◆そもそも太鼓堂とは何か ◆音が聴けるページ ◆CD『江村夏樹 云々』 ◆太鼓堂 CDR屋さん ◆太鼓堂 DVDR屋さん
◆No Sound(このページには音がありません) ◆江村夏樹 作品表 ◆太鼓堂資料室 ◆太鼓堂 第二号館 出入り口
◆いろいろなサイト ◆江村夏樹『どきゅめんと・グヴォおろぢI/II 』