 去年の秋、友達からバルトークの論文集をもらった。講演用の原稿がたくさんはいっている本だが、ぼくの予想とは裏腹にそれは全部英語で書いてあった。生前の彼は作曲家としてではなく、民謡研究家として知られていた。このことは知っていたが、バルトークはハンガリー人で、東ヨーロッパの民謡を研究していたんだから論文もハンガリー語で書いているんだろうという程度の先入見しかなかった。その謬見を覆され、英語で書いていたと知って驚いた。
去年の秋、友達からバルトークの論文集をもらった。講演用の原稿がたくさんはいっている本だが、ぼくの予想とは裏腹にそれは全部英語で書いてあった。生前の彼は作曲家としてではなく、民謡研究家として知られていた。このことは知っていたが、バルトークはハンガリー人で、東ヨーロッパの民謡を研究していたんだから論文もハンガリー語で書いているんだろうという程度の先入見しかなかった。その謬見を覆され、英語で書いていたと知って驚いた。
江村夏樹
70.
「バルトークという作曲家のこと」
 去年の秋、友達からバルトークの論文集をもらった。講演用の原稿がたくさんはいっている本だが、ぼくの予想とは裏腹にそれは全部英語で書いてあった。生前の彼は作曲家としてではなく、民謡研究家として知られていた。このことは知っていたが、バルトークはハンガリー人で、東ヨーロッパの民謡を研究していたんだから論文もハンガリー語で書いているんだろうという程度の先入見しかなかった。その謬見を覆され、英語で書いていたと知って驚いた。
去年の秋、友達からバルトークの論文集をもらった。講演用の原稿がたくさんはいっている本だが、ぼくの予想とは裏腹にそれは全部英語で書いてあった。生前の彼は作曲家としてではなく、民謡研究家として知られていた。このことは知っていたが、バルトークはハンガリー人で、東ヨーロッパの民謡を研究していたんだから論文もハンガリー語で書いているんだろうという程度の先入見しかなかった。その謬見を覆され、英語で書いていたと知って驚いた。
バルトークのピアノ曲を弾くのは難しい。たくさん練習しなければならない。楽譜からじかに読み取れない独特のリズム感覚がこの作曲家の創作の根底にあるということがわかるまでにはさらに時間がかかる。これに気付くためには、たとえ面倒でも、ピアニスト自身の母国語の語感と、バルトークの楽譜に書いてある音情報とをつきあわせて、うまくかみ合う勘所を探さなければならない。それだけではまだ作品や演奏方法の輪郭が浮き出てこないときには、ピアニストは自分と楽譜以外の情報から推察できるバルトークの創作態度を参照する必要がある。こういうときに作曲家自身による手紙や論文があるとすごく重宝なんですが、ややこしいのは、バルトークが東ヨーロッパの民謡について、彼の母国語ではなく、英語で記述したものを各地の講演で読んでいることだ。このことを知ったとき、妙な気持ちになった。よく知られているように、バルトークは1920年代にゾルタン・コダーイと共にハンガリーの首都ブダペストから国内やルーマニア、チェコスロヴァキアの僻地へ旅行し、地元の老婆に昔の歌を歌ってもらい、ロールに録音し、耳と手で採譜した。その体験と成果はバルトークの生まれや育ちと切り離せないし、東ヨーロッパの民謡には国際語としての英語では表現しきれない特有の土着性があるのが本来ではないか。
なんちゃって、こんなことを言っていたらバルトークの音楽世界はもとからなかったことになる。彼は自分の伝統を母国の民謡に求め、その力を信じたから独自の創作もできたし、その創作は単に独自なだけではなくてすこぶる魅力のあるものになった。ぼくたちの問題はその魅力の性質を知ることである。あれほど個性的な外観を呈しているのに、バルトークの音楽は意外に意味を伝えることに慎重な姿勢をとっている。その慎重な姿勢がバルトーク音楽特有の緊張度と結びついているとまでは言い切れないだろう。しかし彼は自国の先輩作曲家フランツ・リストがやったことを引き継ぎながら、自分だったらなにをよりどころに行動するかを新たに模索した。ややもするとぼくたちは、民謡研究はバルトークの創作の直接の手段だったと考えたくなり、東ヨーロッパの民謡それじたいがバルトーク作品の成立事情をわかりやすく解き明かしてくれるような仕組みになっていたらいいなとつい思いがちである。しかし彼の論文はこういう短絡思考には手を貸さない。バルトークの音楽と彼が研究した民謡との関係はそんなかんたんなものではない。都合のいい話はなさそうだ。
ぼくがバルトークの『アレグロ・バルバロ』を初めて弾いたのは14歳のときだった。通学していた中学校の音楽発表会が体育館で行われ、全校生徒300人の前で演奏した。このころ出合ったバルトークのピアノ音楽は他に『組曲』と『ソナタ』、『ミクロコスモス』第6巻から最後の6つのブルガリア舞曲で、『戸外にて』を除くバルトークの主要ピアノ独奏曲に一通り接していたが、どれを弾いてもミスタッチが多く、作品が訴えてくる圧倒的な迫力を腕ずくで組み伏せようとしていた。『アレグロ・バルバロ』はバルトークが30歳のときに書いた曲で、彼がその後のスタイルを確立したと言われている1926年の『ソナタ』のようなバルトークらしさはまだ希薄だが、気持ちはよくわかるというたぐいの小品です。だから、「バルバロ」という語が示すとおり、後の代表作に通じる野性味がこの3分の小品にもよく出ている。ぼくは自分の思春期にこの曲を300人の前でどうにかこうにか披露したという経験が持ててよかったと思う。一般にバルトークを初めて勉強する初心者が弾くのは『ルーマニア民族舞曲』や『ソナチネ』だが、これらの親しみやすい作品は本当はバルトークのバルトークらしさがわかってから弾くべきで、少なくとも平易な入門曲ではない。これらをざつに扱うと、本来必要な細やかな神経とユーモアが見捨てられてしまう。標準ピアノ教則本になったといわれる『ミクロコスモス』でもじっさいのところ、事情はほぼ同じで、全曲を制覇すればいいというような考えがむしろ有害かもしれないという意味の序文をバルトーク自身が書いている。だからこの序文にあるように、『ミクロコスモス』を使ったピアノ学習入門のためには全曲中、苦手な曲は避けて、生徒にあった曲を選ぶのが良いという彼の判断は正しいと思われる。
バルトークの民謡研究が、その民謡じたいと同じようにグローバルなものになりにくいことと、彼じしんの作品の本来の性質がこんにち徐々に認められつつあることとは一見背反しているようだが、ほかならぬバルトークその人がこのパラドックスのからくりを解き明かそうと努力した形跡がある。その成果は完結しておらず、はたの人には晦渋で手に負えないことが多いが、ハンガリーの民謡がうまく歌えなくても、バルトークの作品に触れることで、彼が残そうと努力した東ヨーロッパの土着性の一端を知ることは出来る。それがうまくいった場合に、バルトークの音楽世界の内容と背景がなんなのか、のちの世代が体感できるはずだというのは、単にぼくだけの希望的観測なのだろうか。
ただいま作業中につき、こちらに手が回りませんので、つボイノリオの『恋のいちゃいちゃ』歌詞全文を引き写させていただきます。
恋のいちゃいちゃ 作詞・作曲:藤岡孝章 編曲:野村 豊 うふふ だめよ そんな事しちゃ うふふ 私 そろそろ帰らなくちゃ んふふ いいだろう もう少しだけ だって 今日は 星がこんな綺麗さ フンフンフン あなたとても上手ね 私理性が負けちゃいそう ア、ア、ア、 自然なままで愛し合おうよ 今夜は歩けそうにないわ 今夜は帰さないぞ あなたいけない人ね 君がステキなのさ お願いいじめないで いじめられたいくせに 私の事愛してる? もちろん大好きさ ママにしかられちゃうわ まだまだ子供だな 私もう大人よ そうさ君は女さ だけど少し恐いの 恐いことないさ 優しくしてくれる? 僕のたからもの んふふ ねえ君 口でこばんでも ホラね 身体は うそをつけはしないよ うふふ ばかね お酒のせいよ 何故か とても 身体が火照るの ヘイヘイヘイ いいよ もっと飲もうよ 酔っても何もしないよ ア、ア、ア、 私のすべて あなたのものよ ※ 私もうふわふわ 何もかも忘れていいよ あなたの甘いくちづけ 君の甘いくちびる 誰に教わったの 君のために覚えたのさ にくらしくなるほどよ まだまだこれからさ いけないわあなたそんな事 いいじゃないか君 だめよ あなたそんな事 いいじゃないか君 やめて あなたそんな事 いいじゃないか君 ああ死にそうよ私 もう止まらない僕 ※ ※~※ 繰り返し
なお、つボイノリオ公式サイト「つボイボリオのあっ超~」へお越しの方はこちらからどうぞ。
今日はこれでおしまいです。
 一体、どこまで外国語を勉強したらいいのかわからないことがある。国際化社会といわれ、地球は狭くなったと言われるほど、それとは逆比例して、特定の民族にしかわからない言葉の綾も増えていくように思われる。そしてこのことは国際化社会だからこそ不可欠な困難に数えられていいような気がします。こういうわけのわからなさが、もしなかったら、そもそも国際化社会も狭い地球も意味がない。なくていいということになってしまう。この太鼓堂サイトに英語版が登場して、英文のエッセイを書くことにしたけれど、当初は日本語版のエッセイを訳して載せようと思っていたんですね。ところがこれは、どうにか英語が使えるぐらいのぼくなどには至難の業だということがわかったので、英語のためのエッセイと日本語のそれと、概念を分けてしまうことに決めてしまった。日本人は英語の苦手な民族としてきこえている様子ですが、その要因は日本語のいいまわしと意味との関係が入り組んでいて、自分がわかりきってしゃべっている国語でもいちど、よほど検討してみないと自分が言っていることの成り立ちが見えてこないという性質が、例えば英語に較べるとずいぶん多いという事情があるからではないか。職業的な話術師の場合はよく知りませんが、普段ぼくたちはそんなに全部考え抜いたあげくに言語を発しているわけではない。逆を言うと、書き言葉に対してはかなり意識的だ。どこの国でも同じだよとは思うけれど、日本語でおしゃべりするというのはそれじたい論理矛盾ではないかと思いたくなることがある。視覚情報としての書き言葉と、韻律を重んじる話し言葉とのあいだには断層がある。歴史的にも、日本語の仮名漢字は中国からの輸入品ではないか。
一体、どこまで外国語を勉強したらいいのかわからないことがある。国際化社会といわれ、地球は狭くなったと言われるほど、それとは逆比例して、特定の民族にしかわからない言葉の綾も増えていくように思われる。そしてこのことは国際化社会だからこそ不可欠な困難に数えられていいような気がします。こういうわけのわからなさが、もしなかったら、そもそも国際化社会も狭い地球も意味がない。なくていいということになってしまう。この太鼓堂サイトに英語版が登場して、英文のエッセイを書くことにしたけれど、当初は日本語版のエッセイを訳して載せようと思っていたんですね。ところがこれは、どうにか英語が使えるぐらいのぼくなどには至難の業だということがわかったので、英語のためのエッセイと日本語のそれと、概念を分けてしまうことに決めてしまった。日本人は英語の苦手な民族としてきこえている様子ですが、その要因は日本語のいいまわしと意味との関係が入り組んでいて、自分がわかりきってしゃべっている国語でもいちど、よほど検討してみないと自分が言っていることの成り立ちが見えてこないという性質が、例えば英語に較べるとずいぶん多いという事情があるからではないか。職業的な話術師の場合はよく知りませんが、普段ぼくたちはそんなに全部考え抜いたあげくに言語を発しているわけではない。逆を言うと、書き言葉に対してはかなり意識的だ。どこの国でも同じだよとは思うけれど、日本語でおしゃべりするというのはそれじたい論理矛盾ではないかと思いたくなることがある。視覚情報としての書き言葉と、韻律を重んじる話し言葉とのあいだには断層がある。歴史的にも、日本語の仮名漢字は中国からの輸入品ではないか。
最近、日本語で文章を書いてコンピュータの翻訳ソフトに入れると、ずいぶん不可解な結果が出てくることもありますがとにかく英語に直してくれる。自分の頭でこの結果を解釈して手を加えればどうにか意味が通じる英語になってくれるというわけだが、どうして、あの翻訳ソフトというものはしばしばわけのわからない、失笑を誘う結果を出してくるのでしょうね。ちょっと前、英語版のエッセイにお花見会の話を書いた。
"So the concert was a kind of experimental event for listening to contemporary music enjoying the spring cherry-blossom and wonderful moon."
「つまり、このコンサートは春の桜とすばらしい月を楽しみながら現代音楽を聴くという、一種の実験的な催しだった。」
上の英文の最後のほうの「wonderful」は、はじめは「night」だった。「the spring cherry-blossom and night moon」と書き、試みに翻訳ソフトに入れた。結果は「したがって、コンサートは、春桜花を楽しんで、夜がお尻を出す現代音楽を聞くための一種の実験的な出来事でした」。確かに俗語として「moon」は動詞で「露出した尻を出す」という意味があるそうだし、「night moon」とは意味の重複で英作文としては出来が悪く、普通あまり使わない言い回しだと批判することはできる。しかしひどいじゃないか。そんなに勘ぐらないでもらいたいと、日本語圏の常識的な英語初学者ならびっくりするはずだ。英語圏の人だってここまでいたずらが好きだとは思えない。これを読んでくださる英語圏の皆さんでこの動詞「moon」がなぜ「お尻を出す」という意味に転じるのか、おそらくエロティックな連想から出てくる意味なんでしょうが、学識の豊かな方のご賢察を乞う次第です。
もうひとつの経験はもっと一般的なものだが、ここに「肘鉄を食らわしてやりました」という言い回しがあって、これを英訳しなければならなかった。肘鉄、動詞 elbow では意味が弱いし、「I choped him」は「私は彼をぶつ切りにしました」という怖ろしい意味になり、かといって「elbow chop」とはムリな造語で、結局「I have given him a chop」と無難にやっておいたが、もとの日本語のおもしろさが台無しになって無念は覆うべくもない。
そんなわけで英語に対しても日本語に対しても、およそ文章を書くことに慎重になってしまった。英語を扱うすべての異国人が英文学者のはずはない。John という人名が俗語では Toilet と同義だなどという智恵を中学校で聞いたからといって、アメリカの作曲家 John Cage を不埒千万にも Toilet Cage と置き換えたことはいちどもない。人の名前をジョークに使うのはぼくの趣味ではないことを断った上で、John Cage は Toilet Bracket というような物体をさす名詞だが、いったいこの Toilet Bracket とはなんぞや?こんな悪趣味な文章を書いた罪償いに、せめてジョン・ケージの興味深いピアノ作品を上手に披露いたしましょう。
すんまへん、ただいま工事中につき、まとまった文章を書いたり、このページを閲覧してくださる皆さんとおしゃべりしたいのは山々ながら、作業場がこんなんなっていて事態の収拾には今しばらく時間がかります。というわけでしばし雑談。
ぼくは音楽をなりわいにしていますが、ひとくちに音楽といっても種類がさまざまなのはご承知でしょう。知人に詩人がいて、これもご存知のように詩というものはしばしばよくわからないもので、それは盆栽や生け花の良し悪しと似たようなところがあり、盆栽なら庭に置いておいて手入れをすれば立派になったり枯れてしまったりということは管理する人の手際や技量や愛情次第で、形になったものを持っているということは所有欲を満たすし、植物だって生きている以上、立派になったって枯れたって、形がさまざまに変化するということは、 話が飛躍しますがいまラジオでコレルリの合奏協奏曲ニ長調が終わりました。形がさまざまに変化するということは、それを持っている人を元気にするエネルギーを発散しているということなのですね、なんちゃって。詩が一冊の本で、詩のほうから動かないから読む人が想像力を動かさなければならないというのは、大げさに言えば文学一般の宿命だよね。読者にある種の努力を強いる。活字はそこに置かれたまま動かない。たぶん、知人の詩人はそういう、一冊の本の融通の利かなさをいやというほど知悉しているのでしょう。かつて彼は電話で愚痴をこぼしていた、「いらないって言われちゃえばそれだけのもんだしさ」と。もちろんおおかたの場合、読書は楽しい娯楽で、仕事の合間の趣味の楽しみを提供しうる。だけど読書で得られる楽しみは愉快一辺倒とは限らないよ。読書の快楽を義務教育で教えるべきだ、そのためには小学生に詩を書かせるな、なにしろ教科書に載っている詩には概してろくなものがないと意見した文学者がいました。これは正論である。だから全面賛成できないところがある。賛成できないのは「読書の快楽」という一節で、スペインのマドリッドでテロが起きたらしいですね、ラジオがいま報道しています。「読書の快楽」というのはそもそも、日本語をよく研究した人にしてはじめて言えたことではないのかなあ。だから、小学生にすぐれた詩を読ませよう、愚劣な詩をお手本にして詩の書き方を教えるのは止めようという意見は筋は通っているけれどどこか不自然な感じがする。何より、小学生の言語感覚はまったく未分化なものだ。その感覚に訴える文学にすぐれたものをあてがうというオトナの配慮は、実用的だが、そんなことより、生徒それぞれに好きなテキストを選ぶ自由を許すほうが、それぞれの生徒の資質にもかなって、生徒がそれぞれ自分の審美基準を組み立てる冒険になるのではないだろうか。「優れた詩」というのはオトナが考える基準に適ったものを指していう言葉で、小学生にも判断力はあるにしても、それは理論によらず、大部分感覚による選り分けである以上、彼らの感覚にまかせて好きな本を選ぶ自由を与えることはできないのだろうか。
こんなことを書くと、そんな意見は実際的でない、実現不可能だという反論が出てきそうだが、そうでしょうか。生徒に選択の自由を許すと教室がとんでもない混乱に陥り、教師の労力がとほうもなく膨れ上がるという事態は誰にでも予測できます。でも敢えてしゃべってみたいんだけれど、その重圧を引き受けるだけのうつわのある教師が求められてはいないか。ぼくは、それだけの容量を持ち、かつ、みずからが学校内で不良になったり精神錯乱を起こしたりしない教師は今後増えるだろうと考えている。社会がそれだけの人材を必要としているのは新聞テレビなどの報道で明らかなのに、教師が荒んだりおかしくなってしまったりでは元も子もない。事実は、あらかじめ与えられたテキストをめぐって教室で論議したところで、小利口な文芸評論家が増えるだけじゃないか、という気がする。教室にテキストを与えることはオトナの善意のあらわれだ。何かきっかけがなければ何も始まらないのも事実でしょう。しかしそのきっかけに生徒が陶酔するかどうかは全然別の問題だと思うので、「読書の快楽」を教室で教えるという提案には、何か人間の心理に反する性質が含まれているような気がします。ここでしゃべっていることは実践場面の部分を切り取ったものだから、提案というには取るに足らないかもしれない。でも、なんか気がかりなことには違いない。
以前、小学2年生にピアノを教えていたことがあった。この女の子は、学校の音楽の時間に「ゆめのえんどはめざまし」という曲を合奏しているから、それをピアノで弾きたいと言いだした。楽譜を持ってきてもらったら、音楽の担当教官が手ずから作曲したらしい旋律の楽譜には基本の拍子も調性も書いてなくて、基本、4拍子らしいが、休符があちこちで抜け落ち、これでどうやって全員合奏ができるのかさっぱりわからなかった。その場の雰囲気でなんとなく合奏らしいことになるらしい。百歩譲ってそれはいいことにするとしても、「ゆめのえんどはめざまし」=「夢のENDは目覚まし」では、いくらなんでも情けないよ。こういうばかげた言語感覚が、作曲者であるところの音楽担当教官にどうやって身についたのか知りたいものである。さっき書いた詩の問題と矛盾するようでいて、このふたつは目に見えにくいところでこんがらかりながら抵触しています。慙愧の念に耐えない、とか、断腸の思い、とかいう表現は、こういう事態のためにあるようなものだ。教育の現場に勤務していないぼくが若干名のピアノ生徒と接しただけでこの程度、察しがつくのだから、現場に従事している先生方にはもう少し頑張ってもらいたかったりして。
 工事のことについて何か書けるほど工事の経験があるわけでもないんだけど、「construction」 という英語には工事という意味があるようで、ぼくが日ごろやっている音楽の「構造」とおなじだから工事かな。まあ「組み立て」だよね。工事して出来たものは不動産だとかバイパスだとか、高層ビルだとか、自分にはあまり縁がなくてもなんとなく存在がうらやましいような、近隣にそんなのがあるっていうだけでなんかうれしくなるような(ここらで「ならないよ」と突っ込まれたら話は終わりだが)、と、ここまで書いて、新しいもの好きなだけで、新しいものは別に工事や構造とは関係がないし、新しい構造はいずれ古くなり、新しいマンションなんかも必ず古くなるから、マンションは新しく建て替えるんだけど、それにはお金がかかるから、10年とか20年とかかかって古くなっていくあいだに貯金して、場合によっては地盤沈下で土地が傾いて壊れたり、天変地異(てんぺんちい)だったりで困りますねエ。こういうのって古いほど価値が出るんじゃないの?かんちがいほど感じがいいこともあり、戦前から建っている木造アパートをだれも世界遺産や国宝に指定しようとしないのは、物の価値とは関係がなくて、ケッサクな人物が関係(みだりに想像をたくましくしないようにしてください)していたりすると案外、国宝になりやすいかもしれないから、雨の日も風の日も期待して外で突っ立って待っててみましょう。以上、桜咲き乱れ、こんな夜は国民も乱れ踊ることがあったりなんかするような夜のすばらしく光で照らされた吉野公園から天照大神(てんてるだいじん)が品のよいお酒を適量いただきながら豪快にぶっ放しっぱなしましたー。衛生生ビールもよろしくねッ。
工事のことについて何か書けるほど工事の経験があるわけでもないんだけど、「construction」 という英語には工事という意味があるようで、ぼくが日ごろやっている音楽の「構造」とおなじだから工事かな。まあ「組み立て」だよね。工事して出来たものは不動産だとかバイパスだとか、高層ビルだとか、自分にはあまり縁がなくてもなんとなく存在がうらやましいような、近隣にそんなのがあるっていうだけでなんかうれしくなるような(ここらで「ならないよ」と突っ込まれたら話は終わりだが)、と、ここまで書いて、新しいもの好きなだけで、新しいものは別に工事や構造とは関係がないし、新しい構造はいずれ古くなり、新しいマンションなんかも必ず古くなるから、マンションは新しく建て替えるんだけど、それにはお金がかかるから、10年とか20年とかかかって古くなっていくあいだに貯金して、場合によっては地盤沈下で土地が傾いて壊れたり、天変地異(てんぺんちい)だったりで困りますねエ。こういうのって古いほど価値が出るんじゃないの?かんちがいほど感じがいいこともあり、戦前から建っている木造アパートをだれも世界遺産や国宝に指定しようとしないのは、物の価値とは関係がなくて、ケッサクな人物が関係(みだりに想像をたくましくしないようにしてください)していたりすると案外、国宝になりやすいかもしれないから、雨の日も風の日も期待して外で突っ立って待っててみましょう。以上、桜咲き乱れ、こんな夜は国民も乱れ踊ることがあったりなんかするような夜のすばらしく光で照らされた吉野公園から天照大神(てんてるだいじん)が品のよいお酒を適量いただきながら豪快にぶっ放しっぱなしましたー。衛生生ビールもよろしくねッ。
 年明けから3ヶ月も作曲を続けているうちにピアノの練習の時間が取れなくなり、作曲が終わって、そういえば自分はピアノも弾く人間だったんだと、いまさらのように思い出す始末。長い目で見れば、この一時的な喪失の感覚は、先々の自分の人間形成には必要なことかもしれない。正直を申し上げて、こういうことでもないと、ヨーロッパ音楽を無意識に盲信し、ときに崇拝の対象にしている自分に気がつかない。しかし、いちどはヨーロッパ音楽に接近して自分なりにそのよさも悪さも着こなしてみなければ、ヨーロッパを盲信しがちな自分の性向が見えてこないだろう。ヨーロッパ音楽の不思議な魅力は否定できない。でもこればかりと付き合っていると何かうんざりしてくるのは、たんにヒマな人間だからなのか。
年明けから3ヶ月も作曲を続けているうちにピアノの練習の時間が取れなくなり、作曲が終わって、そういえば自分はピアノも弾く人間だったんだと、いまさらのように思い出す始末。長い目で見れば、この一時的な喪失の感覚は、先々の自分の人間形成には必要なことかもしれない。正直を申し上げて、こういうことでもないと、ヨーロッパ音楽を無意識に盲信し、ときに崇拝の対象にしている自分に気がつかない。しかし、いちどはヨーロッパ音楽に接近して自分なりにそのよさも悪さも着こなしてみなければ、ヨーロッパを盲信しがちな自分の性向が見えてこないだろう。ヨーロッパ音楽の不思議な魅力は否定できない。でもこればかりと付き合っていると何かうんざりしてくるのは、たんにヒマな人間だからなのか。
作曲中、ときどきピアノの前に座って指慣らしをしていたが、本命が作曲だったから、ピアノ演奏のマナーが留守になり、いまごろ、取り戻すのに時間を食っている。作曲というのはある意味、自己中心主義の産物で、ピアノを弾くことでそのよくない傾向を緩和しているんですと白状したほうがよさそうだ。しかし、作曲とピアノがひとりの人間の中でぶつかり合うことから生じる理解もある。本命が作曲だからといって、人の音楽をバカにするつもりは当然、ない。しかし人間が自己中心的だということは、自分で知らないうちにどこかのだれかをバカにしているということだと、心理学者は指摘しております。
どんな音楽をやるにしても、その音楽に対する一定の理解がなければ成り立たない。んで、その理解というのが、技術練習では克服できない場合のほうがたぶん多い。というより、技術練習するためにはその音楽に対する理解が前提で、理解とは興味を持つことから始まって、その音楽をめぐって会話が成り立つことで、その会話は通常、自分自分の母国語で行なうから、たとえば日本人がドイツや中国の音楽に興味を持つとき、ドイツ語での理解、中国語での理解なんて具合にいちいち国籍を切り替えているわけにもいかないでしょうが。だから違う国の音楽に興味を持って、ピアノならピアノを弾いてみたい場合、一応、音が訴えてくる意味と、その音楽を共有することで成り立つコミュニケーションとは区別される。何のことはない、日本人がベートーヴェンをやったから瞬時にドイツ人になるわけがなくて、むしろ日本人のドイツ音楽だからドイツの人も歓迎してくれるさ、ぐらいの感覚がなければ、すぐに戦(いくさ)になってしまうから、必要なのは技術練習よりは自分の国籍がわかることなんだろうな。
とかなんとかウェブでぼやいてみたって、どうもいま、世界はそれどころではないらしく、ぼくのぼやきは無効なだけでなく邪魔でさえある。韓国で大統領がクビになったからといって、音楽を主張してどうなるものでもないような、イラクで人質になっている方々は気の毒だが、天から音楽が降ってきたって戦争はやまないような。
まあ、いいじゃありませんか。ぼくは日本にいて自分の音楽をやって、国外の人と「うちの音楽のほうがいいぞ」「まけるもんか」とか、脚の長さやハンサム度、美人度を競ってみるのも一興ではないでしょうか。これは実力行使という前にギャグである。ギャグなら、ちょっと間違えて乱交パーティーになったって微苦笑畜生。煮ても焼いても食えない代物でも、少なくとも犯罪よりはマシだということになる、とでも書きつけて、自作が駄作でもいいことにしてしまう。してしまいましょう。今日はこれでおしまい。
こんな発言を目にした。インターネット上の論議のネチケットについてひとつの理想的な態度を主張した文書の一部で、著作者は、この文書が「いかなる種類のインターネット標準をも規定するものではありません」と断っている。
リアル・タイム対話サービス(MUD MOO IRC)のガイドライン
・他の環境と同様に、はじめは「聞くこと」に徹して、そのグループの文化を知っておくのは賢いやり方です。
[サリー・ハンブリッジ著(インテル社)1995年10月/高橋 邦夫訳(東金女子高等学校)1996年2月2日]※この文書の全体をお読みになりたい方はhttp://www.cgh.ed.jp/netiquette/rfc1855j.htmlにアクセスしてください。
ぼくが興味を持ったのは、この短い文章の中で著作者が、インターネットコミュニティでのコミュニケーションを「文化」と定義していることである。文化の性質については一切書かれていない。ネット上にコミュニケーションが成り立っていれば、それが「文化」なのだ、とする態度のように考えられる。
以下、ぼくのこのメモは引用文をとりまきながら遠心力にまかせて脱線していく傾向があることをご了承ください。文化一般の性質を考えるのに、上記文献の定義は、何か特殊な性質を含んでいないという点で、とても興味深い。もちろんここで言われているのはインターネットの世界で実現可能な文化、厳密に言うと、その枠組みである。にもかかわらず、上記の「文化」に関する定義のやり方は、それ自体がすでにひとつの文化を形成しているように思う。このことがたいへんユニークな文書の性質を現した。ここで言われている内容は、じつは非常に当たり前のことなのだが、コミュニケーションの性質をこれだけ簡潔、かつ正確に把握した記述はあまり見たことがなかったので、正直言って驚いたし、感動もしました。いまぼくは、ここで言語の正誤表や善悪についてものを言おうとは考えていない。ぼくたちが国外へ旅行してパーティーに参加するとき、一般には、積極的に会話に参加しないと置いてけぼりにされますよということになっているようだし、確かにそのときどきの話題からはぐれて知らない顔をしているのはあまりほめたことではない。しかし、初めて訪れた外国の様子がそんなに最初からわかるわけがないのも、また事実である。自分の国でだって、違うご家庭に招かれたときには自分の家のマナーは通用しないと考えたほうが、意思疎通の入り口としては感覚的に納得できることであり、だからと言って、どこの地域や家庭にも共通する符牒なんか、実際のコミュニケーションの現場では、いちおうみんな聞いてくれるかもしれないが、たいして相手にされないということは、経験のある方も多いと思います。「ではどういう事柄が歓迎されるか」、という話の展開になっていくのでしょうか。
このあいだ電車に乗っていたら、車体の揺れでドアのゴムか何かが軋んで音を立てるんですよ。怪獣映画の、例えばゴジラの鳴き声はとにかくミュージック・コンクレート(現実の音を磁気テープに録音して加工する技術の名称、また、その音楽。具体音楽)の技法を使った合成音声である。そういうものに非常に似ていますが、このドアの軋みは怪獣の鳴き声に聞こえない。なぜかというと、ほぼ正確に平均律に近い聴感覚で音程が聞き取れるからであった。
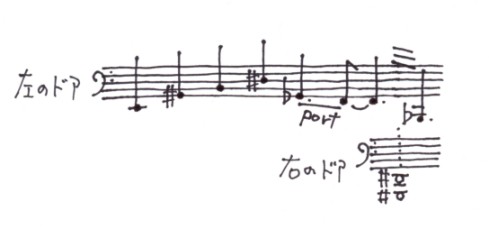
これを聴いたからげらげら笑ったわけでもないし、何か得をしたわけでもないし、ぶっきらぼうというか無性格というか、べつに何も主張していない音である。この音にぼくが感応したとか、意志の疎通があったとかいうようなものめずらしいことは何もなかったが、一定周期でこの軋み音がほとんどまったく同じパターンで繰り返されるため、覚えてしまった。つまり、この電車はしゃなりしゃなりと、月下美人のように夕闇を進んでいました。「車鳴り、車鳴り」と…。それはともかく、この種のパターン認識に関しておもしろい話が展開できることがある。昭和48年3月20日に遡り、東京・駿河台の日本大学理工学部教室を覗いてみよう。
ここに生まれつきのめくらだった人がいて、その人が手術をして眼が見えるようになったとします。ところが、急に物が見えるようになっても、はじめのうちは何を見ているのかはっきりしない。つまり、図形認識能力というのは、眼が見えるようになってからだんだんに発達してくるわけです。心理学者はこの図形認識のプロセスを調べるために、非常に簡単な図形 ― 三角形を見せて、こういう人の視線がどう動くのかを追跡したんです。すると、この人の視線は、だいたい三角形の縁にそって何度も何度もうろうろと動きまわる。それが時間がたってきますと、だんだんと落ち着いてきて、ぐるりと三角形の縁をなぞるようになる。短い時間のうちにそうなるわけです。これで三角形が見えた、と思うわけです。
ところが、われわれ普通の視力を持った大人はどうか?これをやはり同じようにして調べますと、この視線はいちいち三角形の縁をたどるようなことはいっさいしない。詳しい動き方を説明したってしようがありませんが、要するに三角形の頂点の近所をさっと動くだけで、これで三角形認識が出来たというわけです。[笑] われわれ大人は非常に賢く修練を積みまして、きわめて要領よくなっている。いちいちぐるりをなぞってみるようなことはせん。さっきの、途中から眼が見えるようになった人も、ある期間がたってくるとやはりそうなってくる。
ぼくが湯川秀樹の『物理講義』(講談社学術文庫)の最後のこの箇所を長々と引用したのは、もし世の中のあらゆる事象に関して「記述」の方法がなかったなら、ぼくはさっきの電車の軋み音をどう聴いただろうか?ということを考えたからだった。しかしこれは、頭で考えることは出来るが、人間の経験原則にそむいた疑問なのだ。現実には、人は得体の知れないものの正体をなるべく明らかにして、できればそれを記録しておくという方向に、自然に進むからである。湯川博士の講義録はこの自明のことをもういちど、白紙の段階から順を追って組み立てなおしている。
ぼくは五線記譜法の長所についてとか、いわんや自分が五線記譜をいつも取り扱って仕事をしている職能の優劣とかをここで誇張したいのではない。そうではなく、音を使う遊び心があるということは、そこに音があって、ひとはこの音にあるかたちを求める、ということが言いたい。この態度が欠けている場合、音は、あっても取り扱えないものである。取り扱えないというのは、その音の性質がわからないということで、その「音の性質」というのは、音を聞いた人の感覚が働いて生じた主観や客観や具体や抽象やいろんな判断の帰結または道程である。いま目の前に見えるのが犬なのか猫なのか蛇なのか、あるいは動物でなくて鞄(かばん)なのか、とにかく判断しなければ道を先へ進めない場合がある。なんだか知らないが飛び越えようというのは非常に危険な場合もある。相手取っているものが音だからといって常に安全なわけがない。なぜなら、音を聴いている人がいる限り、その人は音にプラスかマイナスか、どちらかの価値を求める場合があるからだ。
話は、電車の軋み音を皮切りに、「街が訴えてくるもの」の相貌へ向かうはずですが、少し長くなったのでひとまずここまでアップロードして、ここから先は近日中に掲載することにしましょう。
前章の冒頭で引用した「リアルタイム対話サービスのガイドライン」のなかで文化という言葉にぶつかって、半分妙な気持ちで街へ出かけると、デパートとか、なぜか目を惹くものはビルディングでした。なぜなのかをちょっと考えてみると、どうやらビルは四角いから、らしいのだ。
その四角いビルと「文化」という言葉がふだん気付かなかったような均衡を保っている。前川佐美雄のこの短歌にあるような一種、理解しにくい感覚とは違うんだけれど、安定した地面の上に垂直に建っている立方体しか街にはない。その街を妙だなと思いながら、しかし、やっぱりこの四角い街にも魅力を感じるぞ。それは自分がこの街を歩いているから遠近法や加速度が心地いいんだろうか。
以前、ある女人と温泉場の羞恥心などについて徹夜で話し込んだことがある。以下はそのときの会話の再現。いきなりなんですか(笑)、論じることじゃないですよ。でもあれってなにげに恥ずかしいですよね。見られることもさりながら、自分が見る視野に入るのがはずかしい。キャー安部公房大好き。『砂の女』『笑う月』素敵ーかなんか言うからさ、話が合うと思って、ぼくは『箱男』が好きだと言ったら、ぎゃー、やめてー気持ち悪い、最初のページ読んだら薄気味悪くて本棚に放り込んだ、ぎゃーお願いやめてーひえー。安部公房の小説読んでると必ず、小便を洩らしそうな男や女が出てくるけど、あれなんでだろ、 小説家ってときどき書くじゃない。うーん…「生(せい)」とかかわるからじゃない?あ。「辱」と「悲」はつながってるのよ。羞恥心失くしたくないです。雑談の途中ですが、ここで安部公房さんご本人にご登場願おう。
…都市に固有の性格として、空間密度の圧縮ということがあげられるだろう。この集中化は、相対的に、人間の移動効率を高め、人間関係も多角化する一方、無名性も強められる。農村生活の定着性にくらべると、都市生活者のパターンは、驚くほど移動民族的な傾向を帯びて来るのである。四角いものがタテヨコに並んでいる街、懲りもせず同じところを何年でも往復している都市生活者。そういえば、安部公房の小説の舞台には垂直と水平の関係が崩れているような変な状況設定がところどころにある。まさか、ぼくが日頃から安部公房的小説世界に住まっていて、この作家の特異性がちっともおかしく見えない感覚の持ち主だという事情でもないはずだ。ぼくはこの作家の『箱男』『密会』『笑う月』『カンガルーノート』などを何度か読み返している。読書途中から、一体なにが書いてあるのかわけがわからなくなることが多いからである。しかしこの一過的な混乱は、安部作品の小説のあらすじが支離滅裂でなってないとか、そんなことを裏書するわけではない。作者が意識していたかどうかは別として、安部作品の空間の設定は、読者を、読者自身の非日常空間に連れ出すという仕組みになっている。だからゆくゆくは安部作品の意味がいずれ腑に落ちるというからくりなのだろう。安部公房の小説の多くが主人公の独白という文体で書かれていて、それは安部公房自身である(と思われる)場合もあるが、そんなことかってに考えていればいいじゃないか、ばかげたことに付き合っていられないよ、では終わらない。『カンガルーノート』に書かれていることは、全部、脛にカイワレ大根が生え出した主人公の妄想らしいが、描写がぜんぜん病的でないところが特徴で、ばかげたことがばかげていないという「ふざけた等式」が成り立っているようだ。この種の等式が現実の空間に具現しにくいのは当然で、しかし記述は出来ないまでも、日常生活にこの等式が伏在しているのはどうやら確かである。(『内なる辺境』中公文庫 96ページ)
安部公房論になってしまいました。いつになっても「街が訴えてくるもの」の本論らしいものが現れないが、周辺をぶらぶらしながらしばらくこのタイトルで連載を続けます。気長くお付き合いくださいますよう、お願いします。乞御期待。
当たり前のことだが、充分な空間がなければ人は動くことが出来ない。満員電車などはその極端な例である。金曜日の終電には乗りたくない。「力尽きた!」と叫ぶ女の子がかりに美女だったとしても、押し潰されそうな車内で相変わらず押し潰されそうになっていなければならない。所属を持ち、集団の中で暮らし、いつも何かの目的のために街に出るのは、空間の奪い合いだ。この競争に参加しない人たちは街を歩いてはいけない、とでも街が金切り声をあげているかに見える。
都心から少し離れて生活していて、よく脚を運ぶCD屋さんは、電車で15分揺られて着く街にある。面白いものをそろえている店なんですが、いつごろからか、この店に行くのがどうも億劫になった。CD屋さんやデパートや街に文句があったわけではない。そうではなくて、家の中でCDを聴く楽しみ方がわからなくなったから、音楽を売っている店に行っても仕方がないといううざったさがつのった。コンサート会場だって密室で音楽を聴かせる場所だし、CD屋さんも自宅も、基本のところで性質に変わりはないと思うものの、なんだか自宅でCDを聴くのが、うまく言えないが、ある期間、厭になった。こんなことは思春期にはなかった。フルトヴェングラーやアンセルメ、ミュンヒンガーといった歴史的指揮者、ピアニストならケンプ、フランソワ、ベロフ、ラーンキ、ポリーニ、グールドのLPをさんざん聴いて飽きなかったのは、まさか学校の勉強のストレス解消だっただけではないはずだ。いまごろになって、さんざん音楽を聴いたから飽きたわけでもない。そういう話じゃなくて。
音があるということは、その音のまわりにも何かいろいろとある、すきまも充分あるということでなければ、満員電車の中で人が動けないように、その音は動きが取れないはずだ。音の動きが取れないんじゃ音楽にならない。居間のスピーカーやコンサートホールでどれだけの音を鳴らしたところで、音を鳴らす人や音響機材も、その音を聴く人も、自分が持っている音のまわりを持っていなければ、音が充分動けない、というような事情に違いない。家でCDを聴くと、楽しめるまえに気が重くなってきた、というぼくの一時期は、どこかに音が過剰な状況を背負っていたから音の自由がきかない、ということだったのだろうか。
通勤電車の優先席にはこんなメッセージが掲げてある。
おゆずりください。
「どうぞ」このひとことが明るい車内をつくります。
おゆずりください。
「どうぞ」このひとことがピカッと明るい車内をつくります。
半袖長ズボンをおゆずりください。
「どうぞ」このひとことがピカッと明るい車内をつくります。

一般社会で通用しない異常な世界を音楽とか絵とか、小説などでの表現は、いかに立派に見えても、単なる代償行為、欲求不満の捌け口に過ぎないと批判されたらそれでおしまい、ということになりそうな場合もあることは否定できない。しようもないつくりもの、独りよがりのつくりものだってあることは確かだ。このことを踏まえて、一般に芸術家と言われている人種は、ことに最近、一瞥して非常識すぎる表現は慎むようになったのかもしれない。わが身のことでもあるのでちょっと言い添えておくと、あるつくりものが人を一定時間、持続して楽しませるものなら、表現内容はどうであれ、その作者は公務をまっとうしている、まともな人間であると断定してよい。まったく、この価値基準は文化や芸術を作る側の良識や美学なんかより、それを受け取る人たちの判断にゆだねられる、という関係が、ほんとうは望ましいのだ。バカなものを相手に忙しい時間を割いていられるほど、人はヒマではない。したがって、外見、いかにふざけた表現を装っていても、充分楽しませてくれるようなつくりものに出会ったとき、その作者は少なくともバカではないと批評される。これが、文化一般に認められるコミュニケーションの正体であることはもっと知られてよい。例の有名な生物学者がこのことについて詳細に論じた『馬鹿力』という本を出版して国内でベストセラーになったから、この本が発明した「なんだこりゃ現象」という流行語については、皆さん周知のことと思います。
精神的なものの生理的特質、というようなものがある。心理学ではどう呼ぶのか知らないが、居心地のいい場所柄というのは、この精神的なものの生理的特質を満足させ潤わせるような場所だろう。この満足のためには、余計なことを考えず、運動に専念して汗をかく、という手口もあるだろうけれど、場が音楽会の場合には、なにより精神を潤わすのだから、やみくもに運動して消耗したりしたら意味がない。
音楽に陶酔できるというのは、その人の精神が音楽という水を得て元気になるようなものだ。現代音楽をはじめとする新しい音楽がえてして普及しにくい理由のひとつに、表向き(あくまでも表向きの話だが)、この、精神を潤わす水の作用の不足があるのではないか。もちろん事実はこれに反する場合がある。どんなに耳あたりのいい音楽でも野性味や力強さを備えていなければ魅力がないし、「面白さ」という別の言葉で形容されるこの魅力は、ひたすら精神の水分であることを志願しているものとは限らない。しかし、どんな音楽も、聴き手の精神の生理をいくらか運動させながら、同時に適当な量の水分を提供する、たとえはどうでもよいが、とにかく気持ちが潤うのでなければ音楽聴いても甲斐がない。話が水でなくて、適当な量の酒を提供するんだったら、音楽だったら聴かなきゃ損、という世論が生じるかもしれない。しかしなにぶん水ですからね。日本の水道水は一般に清潔だから、水なんかうちで飲めばいいので、音楽会に来てまで水を求めたい人口がどれだけいるのかな。とは言え、蛇口をひねっても酒は出てこないとなれば、人は音楽に酒を求める傾きがあるのでしょうか。
この短歌の「ぶっかけてやる」という表現について、俵万智は「今まさに生々しい思いを、作者が抱いていることのわかる表現だ」と評している。確かにそうなんですが、ぼくはこの短歌から、さほど悲劇的な感銘を受けません。それは、主人公が鬼ごろしをぶっかけているものは墓であって、生前の故人や、故人の亡骸に直接、鬼ごろしをぶっかけているわけではない、というような、考えてみれば取るに足らない(ようするにどうでもよい、くだらない)連想があんがい大きく作用しているからだと思う。こうなったら思い切り飛躍しちゃおう。「ぶっかけてやる」「ぶっかけられる」快感を故人と主人公のあいだで分かち合っているような喜びさえ、感じられないか。それに、もう故人のことなんかどうだっていいんだ。ぶっかければそれでいいんだ。好きにしてやれ。そんなメッセージが聞こえてこないだろうか。一種非情でありながら人間的というような心象、儀式とか劇とかを万事大げさに拡大しているような「ぶっかけてやる」行為が、そのわざとらしいジェスチャーにもかかわらず、たいへん自然に感じられる。そう言えば、最近は墓も全部、四角い。昔のお墓は楕円をタテにしたようなのが多かった。街のビルも、四角でした。
 ドミトリ・ショスタコーヴィッチの音楽を批評するのは容易でない。音を扱う彼自身の態度そのものが批評的なため、多様というのか、この作曲家が書く音はたいへんうつろいやすく、絶えず固定観念からすり抜けようとする性質がある。ショスタコーヴィッチが書いた音そのものは見かけは複雑でないのに、音から発信して、音の周囲を満たしている気配が一種特有である。ということは、つまりそれだけの音をこの作曲家が簡潔な形で書いているということだが、彼の音楽を聴いていて気付くのは、調性がどこへ変化しても成り行き任せで、ポリフォニーといっても、違う種類の音を何十種類も同時に放り込んだだけで平然としていたり、なんだか遊びすぎた音の解決はダダイスティックに突然断ち切れて、むしろ場違いな主和音がいきなり出てくるとかいう具合で、いわゆる「音楽的な」音の組み立て以外のところに主要な関心が向いていたのではないか、と思わせるほど、きまぐれな変化音の突発に満ちているということだ。ショスタコーヴィッチの場合、内容にふさわしい形式がないとか、形式が内容をどうしても表現できないとかいうとき、形式が溶解していく場合と、内容が萎縮する場合と、両極に分かれるようで、形式が溶解していく場合のほうが、少しまとまりが悪くてもこの作曲家の生命が聴き手に伝わるようだ。そして『交響曲第5番』のようなポピュラーな作品ではそういう雑多な要素を意識的に減らして、よくまとまって結果が親しみやすくなっている分だけ、時たま、物足りないような感じすら与える。ショスタコーヴィッチのトレードマークであるバカ騒ぎ的な不協和感覚は、たとえそれが彼の作品の完成度を低めている場合がときたまあるとしても、このバカ騒ぎに一種の秩序が聴かれるのは確かで、音楽の流れがどこへどう破綻しても全部ショスタコーヴィッチの資質と言ってもいいような、音楽とその周辺領域に対する旺盛で広大な好奇心が丸出しだ。それは下品とは無縁だが少しそれに抵触するような印象があって、下世話というか世俗的というか、わけがわからなくても親しみが持てるばかりでなく、『交響曲第5番』のような、やや模範的に整頓された書法の作品が示すわかりやすさも、よく聴くと、ずいぶん込み入った表情の変化が人間の根本的な感情の起伏をそのまま描き出したように自然である。調性を基調にしながら、調性音楽の機能を変質させて、極端な場合、調性を付属品のように聴かせることさえある彼の手管は、ひょっとすると、そもそも水面下ではヨーロッパ音楽の伝統と見えているものから本質的にずれていて、あるいは無関係な部分があって、常套的な耳の馴染みで聴くと変なことになり、同時にそこがショスタコーヴィッチの魅力なのかもしれない。もちろん、どんなに壊れてもショスタコーヴィッチは調性音楽の作曲家だ。しかし、このずれの感覚はプロコフィエフやストラヴィンスキーを含む、旧ソ連のほとんどすべての作曲家に見られるが、ショスタコーヴィッチはこのずれの感覚と表現内容が不可分の関係にあることを他の誰よりもよく知っていた。このため、彼の音楽に見られる調性の歪曲は本質的に3度関係や5度関係の調性体系と不整合である。近代ヨーロッパの機能和声の調性感覚にはもとから音楽形式の統一を図る便宜としての性質があって、これを基調として作曲することが最初から内部矛盾をはらんでいたのだとすれば、この調性感覚の枠組みを超えるような野心を持った作曲家が書いた音楽はどれもこれも近代和声の概念に対する批評で、その大規模なものは戯画だということになる。機能和声そのものは、ある程度普遍的な調性感覚をまとめたひとつの体系に過ぎず、別にどんな性格も特質も自分からは言い表さないからである。ベルリオーズの『幻想交響曲』は完全な調性と象徴的な旋律による標題音楽だが、じつは調性や旋律それじたいでは表題的なものを何も表現していない。ショスタコーヴィッチの場合、同じことがもっとぴったり当てはまると言ったら詭弁だろうか。
ドミトリ・ショスタコーヴィッチの音楽を批評するのは容易でない。音を扱う彼自身の態度そのものが批評的なため、多様というのか、この作曲家が書く音はたいへんうつろいやすく、絶えず固定観念からすり抜けようとする性質がある。ショスタコーヴィッチが書いた音そのものは見かけは複雑でないのに、音から発信して、音の周囲を満たしている気配が一種特有である。ということは、つまりそれだけの音をこの作曲家が簡潔な形で書いているということだが、彼の音楽を聴いていて気付くのは、調性がどこへ変化しても成り行き任せで、ポリフォニーといっても、違う種類の音を何十種類も同時に放り込んだだけで平然としていたり、なんだか遊びすぎた音の解決はダダイスティックに突然断ち切れて、むしろ場違いな主和音がいきなり出てくるとかいう具合で、いわゆる「音楽的な」音の組み立て以外のところに主要な関心が向いていたのではないか、と思わせるほど、きまぐれな変化音の突発に満ちているということだ。ショスタコーヴィッチの場合、内容にふさわしい形式がないとか、形式が内容をどうしても表現できないとかいうとき、形式が溶解していく場合と、内容が萎縮する場合と、両極に分かれるようで、形式が溶解していく場合のほうが、少しまとまりが悪くてもこの作曲家の生命が聴き手に伝わるようだ。そして『交響曲第5番』のようなポピュラーな作品ではそういう雑多な要素を意識的に減らして、よくまとまって結果が親しみやすくなっている分だけ、時たま、物足りないような感じすら与える。ショスタコーヴィッチのトレードマークであるバカ騒ぎ的な不協和感覚は、たとえそれが彼の作品の完成度を低めている場合がときたまあるとしても、このバカ騒ぎに一種の秩序が聴かれるのは確かで、音楽の流れがどこへどう破綻しても全部ショスタコーヴィッチの資質と言ってもいいような、音楽とその周辺領域に対する旺盛で広大な好奇心が丸出しだ。それは下品とは無縁だが少しそれに抵触するような印象があって、下世話というか世俗的というか、わけがわからなくても親しみが持てるばかりでなく、『交響曲第5番』のような、やや模範的に整頓された書法の作品が示すわかりやすさも、よく聴くと、ずいぶん込み入った表情の変化が人間の根本的な感情の起伏をそのまま描き出したように自然である。調性を基調にしながら、調性音楽の機能を変質させて、極端な場合、調性を付属品のように聴かせることさえある彼の手管は、ひょっとすると、そもそも水面下ではヨーロッパ音楽の伝統と見えているものから本質的にずれていて、あるいは無関係な部分があって、常套的な耳の馴染みで聴くと変なことになり、同時にそこがショスタコーヴィッチの魅力なのかもしれない。もちろん、どんなに壊れてもショスタコーヴィッチは調性音楽の作曲家だ。しかし、このずれの感覚はプロコフィエフやストラヴィンスキーを含む、旧ソ連のほとんどすべての作曲家に見られるが、ショスタコーヴィッチはこのずれの感覚と表現内容が不可分の関係にあることを他の誰よりもよく知っていた。このため、彼の音楽に見られる調性の歪曲は本質的に3度関係や5度関係の調性体系と不整合である。近代ヨーロッパの機能和声の調性感覚にはもとから音楽形式の統一を図る便宜としての性質があって、これを基調として作曲することが最初から内部矛盾をはらんでいたのだとすれば、この調性感覚の枠組みを超えるような野心を持った作曲家が書いた音楽はどれもこれも近代和声の概念に対する批評で、その大規模なものは戯画だということになる。機能和声そのものは、ある程度普遍的な調性感覚をまとめたひとつの体系に過ぎず、別にどんな性格も特質も自分からは言い表さないからである。ベルリオーズの『幻想交響曲』は完全な調性と象徴的な旋律による標題音楽だが、じつは調性や旋律それじたいでは表題的なものを何も表現していない。ショスタコーヴィッチの場合、同じことがもっとぴったり当てはまると言ったら詭弁だろうか。
先日、NHK・FMでショスタコーヴィッチの『交響曲第3番』を初めて聴いた。旧ソ連政府からの委嘱をうけて作った曲らしい。ぼくはこの作曲家を高く評価する。大好きな作曲家である。と改めて断った上で言うが、この『交響曲第3番』は、成立事情はどうあれ、なんだか馬鹿っぽい音楽だ(吉田秀和は、この曲と、その前の『交響曲第2番』の長所を認めた上で、両方を“キワモノ”と評している)。30分ぐらいの単一楽章、終盤で混声合唱が加わり、国を讃える。ルドルフ・バルシャイの指揮がオーケストラをうまく統率している。演奏は良いが、いったい、本気で書いた曲なのかい。国を賛美する交響曲である。聴いていると、政治的メッセージが曲調やオーケストレーションの意図するところとなじまない。共産主義を讃える平明さが音楽の純度を見かけ上は高くして、実際は案外充実していないがそれでもいいようなこの曲調を「気楽さ」とでも言えばいいのだろうか。明るいぶんだけ救われた気分にはなるが、救われて、一体なんだこのおめでたい気分は、というような白痴的な表情がある。そこにこの曲の魅力があるから、なおさらおかしな気分だ。何かのイデーが先に立った音楽は、そのイデーを生かすぶんだけ音楽を貧しくする結果になるのではないか。この曲は、よく言えば単純明快な外観を装っている。その単純明快な外観が頓珍漢な魅力になっていて楽しいのは大いにけっこうですが、野次のひとつも飛ばしたいようなヤケ気分が残る。作曲家はどんな顔をしてどこを見ているのだろうか。時節柄、慎んだほうがいい評論になるが、いまの北朝鮮のプロパガンダみたいなものを思い起こさせる。ショスタコーヴィッチは『交響曲第3番』では迷っても悩んでもいないようで、彼がソヴィエト共産党に対して批判的だったらよくこんな作曲が出来ましたと、その肯定的な態度を「思い切りラジカル」と形容しようと思えば出来ないこともないような気分にもなるが、実際はそこまで踏み切るほど、こちらには共感がなさそうだ。こういう作曲の姿勢を職業的無関心というかどうかは言葉の綾だが、どこか、国家のイデオロギーと切れていないとこの作曲は出来なかったはずだ。というようなことを考えながら無責任に曲を面白がるのは、からかうのとも似てますけれども、かといって馬鹿にしているわけでもない。総じてぼくは、こんなことが考えられる程度には気持ちのゆとりがあると思うことにしよう。作曲者および聴衆のこの態度の性質についてあちこちの角度から調べてみるのは、まんざら無益でもないという気がするので、いろいろな場合について、この態度のありようを、いっそ調べてみたい気分に駆られている。ただし、ことは政治にかかわっているから、問題の作品を単に研究分析するだけでは面白くない。というわけでこの小論はまたしても「街が訴えてくるもの」をめぐって、ああだこうだとそこら辺をうろつきまわることになる。『交響曲第3番』だって街が訴えてきたもののひとつなのだ。
『ショスタコーヴィッチの証言』という有名な本がある。いろんな事情から、ぼくはこの本をまともに読んだことがまだなく、今日、ついさっき文庫版を買ってきた。これは晩年のショスタコーヴィッチが旧ソ連の共産主義やそのほかの関心事について忌憚のない意見を述べたもので、部分的には人から借りて読んだことがあります。これとは別に、プラウダ批判以降のショスタコーヴィチは破滅した、なんて意見を言う人もいる。ぼくは政治音痴ではないが、こんなふうに政治との関連でショスタコーヴィッチを批評すると、20世紀の大問題のひとつである旧ソ連の共産主義の性質がわかってくる(そしてこのことは重大である)代わりに、今現在、ショスタコーヴィッチの音楽が提起しうる意味を見落とす結果になるような気がする。さしあたり未読の本は読むとしても、この作曲家の音楽を、政治的なイデオロギーを抜きにして聴いてみるのは無駄ではない。これは従来のショスタコーヴィッチ像に意味の変容をもたらす可能性があると思います。彼は15曲の交響曲と、15曲の弦楽四重奏曲を書いた。ひょんなきっかけから、いまこの両方のシリーズをいずれも第1番から、順を追って全曲、CDで聴きなおしているところです。久しぶりに居間のオーディオセットの前で長時間を過ごして、夕方、本を買いに街に出てみると、書店には意外に美人がいないこともなく(立ち読みする女性の横顔は美しいものです)、喫茶店は適当に繁盛し(会社員が宴会のようなことをやっていたが陽気で屈託のない店内)、街頭も電車の中も、何のことはない雑多な顔が行き来する日常が相変わらず続いている。街の匂いと春風が心地よかった。
それは5月11日でした。何だ、この暑さは。30℃を超えたぞ。たまらないわ。うちでコンピュータのメンテナンスとピアノの練習をやっていたが、こうも暑くてはこらえ性がない。日が傾いたころを見はからってJRの駅ビルに行く。と、喫茶店で「抹茶クリーム・アイス・ラテ」を売っているではないか。おいしそう。わー。好奇心半分で試す。期待にたがわず美味だった。抹茶とクリームが美しいハーモニーを奏でていました。どのように美しかったかはさしあたり、三島由紀夫に倣って、
『恩が苦』という小説の書き出しです。寒そうな題ですが続きは自分で考えてください。
その喫茶店で、ちょっと気の利いた抹茶クリーム・アイス・ラテを飲みながら本を読んでいたら、隣の席に、糊のきいたセーラー服を着込んだ女子高校生の2人組が、なんだか気がかりな腰つきで、しかし店内のだれた気分をまぶしく刷新しながら駆け込んできた。両手に運んできたものは2人ともメロンソーダだろう、緑の液体だった。清楚な印象のある、プロポーションのいい2人だった。きっと運動部に違いない。ビデオに撮っておこう。しかし、繰り返すが、2人はなんだかやたらに落ち着かない物腰で、並んで椅子に半分腰掛け、背中をかがめてひそひそ話し、くすくす笑っている。心当たりのある雰囲気だ。ひとなつこそうで、こちらは隣にいて、妹にしたいような誘惑に駆られ、「犯罪」の二文字を前頭葉に掲げて戒め、横目で様子を伺っていた。校則を破って喫茶店に入ったスリルと後ろめたさなのでしょうか。紺のスカートの裾から100円硬貨が一枚、床に滑り落ち、音を立てたがまったく気付かない。落ちましたよ。あ、すみません。勉強が出来そうな感じの片方の女学生(劣等生だったとしてもこの話には関係ないッ)がぼくを斜めに振り返り、頭を下げた。この世に生を享けて、たまにはいいじゃないか的悦楽のあどけなく、そのくせどこか大人びた(いいかげんにしろよ)この2人、なかなか嫁に行きそうになく、もうしばらくは街に漂っていて、いつまでもセーラー服姿のまま高校を卒業しそうにない時間のたゆたいを生きている(困るじゃないか)。この娘たちにも両親がいて、うちに帰ったらカレーライスか焼魚か、なんにせよ晩飯を食べて、年若い女の無邪気な脱衣と即物的な入浴を済ませてとっとと寝るのだろうか。天体望遠鏡で星空を眺めて夢見たり、そのあとにもなんかあるのだろうか。現実は黙している。ぼくはこの2人の自宅を訪問したことがない(あたりまえだろうが)。しかし…無遠慮というのか、ごそごそ、がさがさ隣で何やっているんだろう。メロンソーダがいっこうに減らないじゃないか。何しに来たの。そのうち、何を喜んでいるのか知らないが、いたいけな声できゃあ、と小さく叫ぶなり、店を駆け出していった、馬鹿野郎、財布を忘れて。どうやらその財布はこの喫茶店の責任で、警察に届けられたらしいんだが…。
 土曜日の朝のNHK・FMで『Weekend Sunshine』というポピュラー音楽の番組をやっている。DJはピーター・バラカン(テクノ世代にはおなじみの名前です)。ぼくは自分のウェブサイトではめったにポピュラー音楽について書かないが、リスナーとしてはクラシック一辺倒ではなく、どんなジャンルの音楽でも聴く機会があれば楽しむほうである。ピーター・バラカンは世界のポピュラー音楽のすぐれた鑑賞家で、上記『Weekend Sunshine』では批評家としても、スポークスマンとしても広範な手腕を発揮しています。そのことには好感が持てる。ただ、ここからはぼくの趣味なのだが、ポピュラー音楽に関する限り、ぼくは居間のFMでではなくて、生で聴くほうが俄然好きだ。
これは自分がポピュラー音楽の専門家でないことにも起因していますが、エンターテイメントのコミュニケーションの性質が居間のスピーカーやバラカンのDJとそぐわなくて楽しめない場合がある。もちろん、バラカンのような鑑識眼のあるポピュラー音楽の聴き手はユニークな存在で、ときに辛辣な批評も交えるあたりの話術の間合いは痛快だし、必要性といっては話が堅苦しくなるけれど、こういう人がいないとポピュラー音楽はおかしな方角へいってしまう可能性が、いまの社会には充分ある。こういうことは承知で、だが、しかし、レコードで聴くポピュラー音楽はどこか動感が欠け、床の間に鎮座しているように感じられるので、本当はライヴで聴いたほうが面白いに違いないという気持ちがつのる。だからぼくはこの番組を毎週ではなく、気が向いたときにチェックすることにしています。この番組の愛好家の方々の邪魔をしたくないので、雑感としてこちらにメモしておきましょう。この番組から拾い上げて得をしている事々は少なくないことを付け加えます。
土曜日の朝のNHK・FMで『Weekend Sunshine』というポピュラー音楽の番組をやっている。DJはピーター・バラカン(テクノ世代にはおなじみの名前です)。ぼくは自分のウェブサイトではめったにポピュラー音楽について書かないが、リスナーとしてはクラシック一辺倒ではなく、どんなジャンルの音楽でも聴く機会があれば楽しむほうである。ピーター・バラカンは世界のポピュラー音楽のすぐれた鑑賞家で、上記『Weekend Sunshine』では批評家としても、スポークスマンとしても広範な手腕を発揮しています。そのことには好感が持てる。ただ、ここからはぼくの趣味なのだが、ポピュラー音楽に関する限り、ぼくは居間のFMでではなくて、生で聴くほうが俄然好きだ。
これは自分がポピュラー音楽の専門家でないことにも起因していますが、エンターテイメントのコミュニケーションの性質が居間のスピーカーやバラカンのDJとそぐわなくて楽しめない場合がある。もちろん、バラカンのような鑑識眼のあるポピュラー音楽の聴き手はユニークな存在で、ときに辛辣な批評も交えるあたりの話術の間合いは痛快だし、必要性といっては話が堅苦しくなるけれど、こういう人がいないとポピュラー音楽はおかしな方角へいってしまう可能性が、いまの社会には充分ある。こういうことは承知で、だが、しかし、レコードで聴くポピュラー音楽はどこか動感が欠け、床の間に鎮座しているように感じられるので、本当はライヴで聴いたほうが面白いに違いないという気持ちがつのる。だからぼくはこの番組を毎週ではなく、気が向いたときにチェックすることにしています。この番組の愛好家の方々の邪魔をしたくないので、雑感としてこちらにメモしておきましょう。この番組から拾い上げて得をしている事々は少なくないことを付け加えます。
このあいだ、と言っても4月3日、1ヶ月以上前のことになるが、ピアニスト・大須賀かおりとヴァイオリニスト・甲斐史子が組んでいるデュオ《ROSCO》のライヴを聴いてきた。渋谷という街のど真ん中に『公園通りクラシックス』という会場が店開きしたから、ROSCO のふたりはここを活用するんだと言う。60人ぐらい入るのかな、ドリンクなんかも出してくれる。気さくなスペースだ。この日の客演はクラリネットの菊地秀夫だった。菊地さんも含めて、3人とも、日本の現代音楽界で経験豊富な人たちだから、この渋谷のオープンスペースの場合に限らず、ROSCO ライヴの従来からの選曲は新しい曲が多いんですが、極力、深刻なイメージの曲は避けているように見えるけど違うかな。ヨーロッパ文化圏で知られている作曲家を選んでいることが多いが、アルゼンチン生まれのカーゲルだったり、ピアソラのタンゴだったり、ストラヴィンスキーのようないわゆる亡命音楽家だったり、ジャック・イベールやダリウス・ミヨーといったフランスの作曲家を選んでも、めったに演奏されない作品だったり、日本の現代音楽をやる場合でも、その比類のなさ、あるいは類型のなさのおかげで日頃は目立たないという性質の仕事を遺して夭折した甲斐説宗だったり、という按配で、要はライヴの形式が型どおりではない。ROSCO は昨年、クセナキスの難曲を披露して騒がれましたが、自分たちのライヴでは、必ずしもこのたぐいのセンセーションを狙っていないらしい。その柔軟で独自の姿勢が聴きものです。『公園通りクラシックス』は以前、代官山にあったスペースが移動してきて、『代官山クラシックス』から『公園通りクラシックス』へと名前が変わったもので、以前の『代官山クラシックス』でも ROSCO は 地道にライヴを続けていた。ぼくが聴いた限りでは、ROSCO が今まで取り扱った作品の中で規模が一番大きいのは、プロコフィエフの『ヴァイオリンソナタ第1番』である。これは古典の名作で、忌憚のない演奏を聴かせてもらったあたりは、評判になったクセナキス作品のパフォーマンスを上回る充実を示していた。偉そうに構えることと充実していることは別だ。ROSCO ライヴの曲目・構成・トーク・演奏は、一見、わかりづらくて誰も聴かない現代音楽を水で薄めて巷に啓蒙するボランティアと間違われやすそうでありながら、その実、だれもそんなふうに間違わないようなつくりになっている。それは現代音楽の世界で非常に実現しにくい種類の楽しみを提供しうるものだ。なるほど演奏じたいも場所柄もテクスチュアは薄いかもしれないし、圧倒的な迫力の演出も稀かもしれない。しかしそういう体験には、他にもっとふさわしい催しがあるだろう。ROSCO のライヴ会場にある空気はなによりも、聴き手への思いやりを主張している。このライヴ活動が継続したら、ある月並みでない気安さをみんなが喜ぶことになると思う。ふたりの外面的魅力については衆目の一致するところであるが、今日日、世の男も女も、色気に安請け合いしないことが存在条件のひとつであることを強要されているようですから、ROSCO のライヴには、ぜひともこの猿轡を解いても犯罪にならないような、着こなしのきく雰囲気が見えるので、今後どんな展開で継続していくのか期待しております。
音楽も含めて、およそあらゆる営みの技術的な側面について充分な配慮が欠けている場合、それは暴力的な作用を持つことがある。でも、暴力そのものかというと、違う、という気がする。自分を否定してかかろうとする批評的態度。誰にでもある心的属性だ。これが反乱するのを怖がる気持ちが個人個人で異なるとは思えない。個人個人で違うのは、この属性に対して意識的かどうかということと、そもそも誰一人として同じ性質の批評的態度を持っていない、ということだろう。自分が何を見聞きし、どんな行動をしているかという全体を見失わなければ、当座は、この暴力的で否定的な態度を受け入れることによって、充分な視野と自己管理を失わずにすむという衛生が必要なのだ。これは、残念ながら、当座の問題をどうにかしのぐ処方以上のものにはならないが、だからと言ってもっと長期的な鳥瞰を望むのはあまり現実的ではないし、生産的でもないと思う。もちろん、長期的な計画は必要だが、ぼくがいま言及しているのは別の事柄である。ことを始める前に充分な準備をしても、非常にしばしばぼくたちは乗り越えにくい壁に突き当たるし、ある場合には、その壁を乗り越えるのが不可能に思える場合もある。そこで、ぼくたちの心の中には乗り越えられない壁というものがあるのかどうか、訊いてみたいんです。確実な不可能はある。深い海底で声をあげて歌をうたうことは出来ない。鼻で昼飯を食うことも出来ない。車を使った飛行も同様です。だけどそういう事態を想像することは出来る。一見、こういうたぐいの想像は別に暴力的でないように見えるし、実際、被害は少ないかもしれない。でも、想像がくだらなさ過ぎると、失望や絶望を引き起こすかもしれない。駄洒落に絶望して生きる希望を失う人がいないとはいえない。そういうことになれば、人はなんにも想像しないのが有益だという結論が出てくることになる。どんな冗談も洒落も通じないとなったら、人は絶対確実な事実しか口にできないことになる。そのくせ、絶対確実な事実ばかり云々しているうちに、その事実がほんとかどうか疑わしく思えてくるのが人間だとすれば、冗談、洒落、ウソのたぐいが日常にあったほうが、人生も社会も潤うというものなんじゃないか。
 あなたのたくましい想像はたいへんけっこうですが、「中へ入っていくこと」は面倒なことだと、一般に考えられている。禁を犯して入っていけば犯罪になってしまう危険もはらんでいるとみんな思っているだろう。鎖で縛り、紐を両側から引っ張って解いて、扉をこじ開ければ入り口が見えやすくなることは誰でも知っているが、扉はそう簡単に開いてくれないことは誰でも知っているが、たとえ入り口がはっきり見えてもすぐに中へ入れるわけではない。むしろ外に出るほうがたやすいかもしれないが、中に入って、やすやすと外に出てしまったらそのほうが心配だ。私たちはあまりに長いあいだ、いかにして中に入るかを考えすぎた。それは、実際にはそんなに重要な問題ではなかった。ただ、中に入って、そのあとで外に出たときがこわいので、入ることをためらうあまり、いかにも、中へ入れないような気持ちになっていたというのが真相ではないだろうか。奥深い内部に入ろうと思うときには、外に出ることを充分考えておかないとたいへんだぞ。
あなたのたくましい想像はたいへんけっこうですが、「中へ入っていくこと」は面倒なことだと、一般に考えられている。禁を犯して入っていけば犯罪になってしまう危険もはらんでいるとみんな思っているだろう。鎖で縛り、紐を両側から引っ張って解いて、扉をこじ開ければ入り口が見えやすくなることは誰でも知っているが、扉はそう簡単に開いてくれないことは誰でも知っているが、たとえ入り口がはっきり見えてもすぐに中へ入れるわけではない。むしろ外に出るほうがたやすいかもしれないが、中に入って、やすやすと外に出てしまったらそのほうが心配だ。私たちはあまりに長いあいだ、いかにして中に入るかを考えすぎた。それは、実際にはそんなに重要な問題ではなかった。ただ、中に入って、そのあとで外に出たときがこわいので、入ることをためらうあまり、いかにも、中へ入れないような気持ちになっていたというのが真相ではないだろうか。奥深い内部に入ろうと思うときには、外に出ることを充分考えておかないとたいへんだぞ。
内容を示されたとき、その内容が理解できなければ、どんな内容もわけのわからないものだ。この理解はぼくたちの感覚、経験、想像力などから出来た意味の塊で、それが固定しないで運動を続けているというところが肝心である。ぼくたちは真空にひとりでいるのではなく、さまざまな環境から影響や刺激を受け続けながら、自分の意味を絶えず更新している。意味の更新のためには、更新しても良いだけの準備が必要で、この準備がないと自分や外界の刺激の変化に押し流されてしまう。押し流される快楽なんてのもあるらしいし、逆に、絶対押し流されない剛体のような心もあるんだとさ。ぼくたちは、ふやけた現実といつも、どこか隣り合わせに生きている。別に努力しなくてもわかってくることはあるもので、ふやけていることと怠けていることは別物らしい。成長しない人間は死んでいるのだとも言える。生きていればいやでも成長する。努力というのはこういう生理的・身体的な現実を踏まえて、それに逆らわないような配慮で行なうときには効力があるが、無理やり努力するのは原則に矛盾している。それでも努力してみたいのは、よくよく理由のあることなのだろう。
入っていいだけの条件を満たす必要があるのでしょうか。条件つきでないと入れない内奥なのでしょうか。
しかし、或るとき、ふと考へたことであるが、何事をするにも几帳面であると言ふことは、さう誉めたことではない、と思つたものである。決めたことを決めた通りにすると言ふのは、誰でもやることである。しかし、人生のことは、決めた通りに出来ないことが多い。そんなとき、決めた通りではなく、いつそ、ぞろつぺいにやつて了ふ方が、積極的で、面白いことがたくさんあるのではないか。宇野千代のこの文章は、決めた通りにやるのではなく、ぞろっぺいにやったほうが面白い、なんてことが言いたいのではない。でもこの文章によると、一度、ぞろっぺいにやってごらんなさい、ということになるかもしれないよね。しかし、結果は、面白いかもしれないが、ぶざまかもしれないのだ。
(宇野千代「一種の冒険」から。中公文庫『私はいつでも忙しい』に収録。)
何だかよく見えないまま、とにかく入りました。どんな感じ?いいアイデアが出そう?…そんなことより、ぼくたちはすでに、とっくの昔から中に入っていることに気付いていないのだ。いつだったかはわからないが、とにかくぼくたちは大胆不敵に中へ踏み込んで、居座った。中に入ったままでいたことに、こんなにも長いあいだ気付かなかったのだ。外に出なければならないが、長いあいだ中に入っていたにしては、いや、長いあいだ中に入っていたからこそ、自分がどこに入っていたのか忘れてしまって、出ることさえ考えていなかったのだ。外へ出るには、いまいるところがどこかを知らなければならない。入れて、出すだって?入れてもらわなくても、とっくに入っているじゃないか。20世紀はこの事実を忘れて、とにかく入れることばかり考えて、出ることのほうは忘れていた。中へ入ってみなければどうやって外へ出たら良いかもわからないというわけか。中の様子がわからないうちは入る勇気がなく、中に入ってるときはそこが中だということに気がつかず、気がついたときには外に出るすべを知らない、これでは入れないし、出られないということとそう違いはない。なんですか、では、いつもこれから入るところで、すでに中にいて、出ている、というわけですか。あのー、新参者ですが、どういうパーティーなんですか?あちゃー、パーティーではない?もう終わったんですか。期待はずれではなかったでしょうって、私は新参者ですよ。まだ入ってない。ああ、まだやってるんですか、え?参加の仕方は、ただ立ってるだけ?入場から退出までずーっと同じ場所に立ってるんですか?なんですって?入るためには、大きく広げること?要点を突いて当たることが大事だって?気をつけてないと出るときがたいへん?(いいかげんによしなさいよ。誰だ、こんなこと言っているのは。)
きのう2ヶ月ぶりに渋谷に行って、街は相変わらず散らかっていたけれど、昼飯時、簡易飲食店で飲んだオレンジジュースが逸品だったのでほかのことはどうでもよくなった。客(ぼくのことです)が見てる前でミカンを3つも絞るんですね。感激したなあ。どこのミカンか、なんて野暮な詮索はしないで、うれしかったなあ。
だいぶ前、このページで、精神科医の故・宮本忠雄氏の論説を引用したことがある(「11.」2002年1月31日木曜日)。あれから2年以上経って、再び、この論説が意識にのぼってきた。この2年のあいだにぼくの日常や環境がいろいろ変化して、以前は気付かなかったが、いま時点ではわかりそうなこともいろいろ出てきた。いちいち、以前のページを開いていただくのは煩瑣だと思うので、もういちど引用しながら、いま関心があるところを披瀝したいと思ってるんですがうまくいくかなあ。
宮本氏が語っているのは要するに言語の意味の問題で、以下に実存主義や分裂病を挙げて論じている焦点は、ぼくたち人間がコミュニケーションを行なうときに「なにを相手取っているか」ということである。この「相手取っているもの」の正体はなにかということをめぐって、宮本氏はいくつかの症例を検証しているが、もっとも奇怪なものをひとつだけこちらに引くことにする。精神分裂病(現在の「統合失調症」)の患者の談話(筆録)である。
あなたは偉いですよ。そまつにする奴は罰が当たる。虎が出たら一丈一尺。そのとおり間違いなし。いやもう有難うございます。なんともいえない。めんじょうはんしょう、ぱしゃあぼうが、きどものじんたい、なかんなきなく、むかしゃあかんぼだい、そりやあぼげ、びようかんしょく、飲まず食わず……。シヤというのはそうにんで、よんでこうだ、ああだと論じあうところが……。シヤの関係というて別にこうああというシヤに持ちこんで。しりあとが来て聞こえますが。知った人に聞かせると、しまいに医者に言うので。医者がまわしている者が悪人でございますが。本来は医者たるものは正直にしてどこまでもしなければなりませぬ。けれども医者のまわしたるものは悪人であると存じます。悪人と二心たるの注意は内と心と違わぬ。注意ある人びとが悪人ということがどうも反対いたします。二心ありますから畜生と言ってよろしゅうございます。目と心とどうしてよい……。以下、宮本氏の著作から引用する立論には、分裂病の少女ルネなど、実在の人物が登場する。
たとえば、スイスの精神科医デュスは、セシュエー夫人のあつかった分裂病の少女ルネの病的体験が多くの点で実存主義的作家、とりわけサルトルの二、三の小説の主人公、たとえば、『嘔吐』のロカンタン、『猶予』のダニエルらにより報告される「実存的」経験と共通していることを確認し、積極的に「分裂病者における実存的経験」を指摘している。だが、アメリカのスターンのように、むしろ「実存主義者の分裂病的経験」のほうがより真実に近いと主張する見方もある。いずれにしても、人間の実存的地層における諸体験が非日常的な、というよりも、日常性のなかに埋もれた事物や事象のもっとも源初的の意味をあらわにしてくれることは確かである。そして、「事物の実存と無償性を発見したことは、ロカンタンにとって、嘔気をもよおすほどに恐るべきこと」であり、「ルネも自分の存在が完全に無償であることを見いだしたときに、この嘔気を感ずる」。両者の相違は、相手取っている対象がものなのか人なのか、というところだけだ。ものと人とでは事情が変わってきそうだが、実はほとんど差がない。
たしかに、ここでは、分裂病的体験と実存的体験との境は消え去るしかないが、しかし、それらを超えたところに新しい世界の相貌がひらけているようにみえる。宮本氏は実存主義文学の事例と、現実で一般人に起こりうる実存主義的体験を同一視していますが、じつは同一のものと見たのではなく、混同しているのではないだろうか。両者に共通するのはある種の緊張状況だが、一般に、文学の中の緊張と、日常の緊張は別なものである。そんなことあたりまえじゃないの、とは思うけれど、この、無視できない区別をここで強調するのは不自然かな。両者は非常に似ていることは確かだ。「嘔気」という生理的な感覚が、現実を相手取って、頭をもたげてくることなんていくらでもあるが、それを理由にして分裂病的体験と実存的体験との境は消え去るしかないなんて、そんなこと、宮本氏はどこにも書いていない。ただ、書いてはいないが、さも書いているように話が滑ってしまわないだろうか。嘔気を催した人と、催していない人とでははっきりちがうが、ひょっとして違わないかもしれない、というようなことが言いたいわけでもなさそうだ。ということになると、分裂病的でもあり、実存的でもあるような「嘔気」の体験は何かということがわからないと、そういう体験を超えたところにある「新しい世界の相貌」というところまで、話がつながっていかない。そして、「新しい世界の相貌」は、そんなに明瞭に現前するものなのだろうか。例えば、「雑踏の中で倒立した人を見て慄然とする」という体験があるとして、それはほとんど例外なく想像の産物だろう。その想像がたとえ妄想にせよ、病的であるか否かという問題とは別なのではないか。こういうことをもって「境」がないという立論があるとすれば、話の運びが少し強引である。問題の焦点は、「病的体験」を経験したと告白する主体(個人)の精神や心理に踏み込んだところに置かれなければならない。という具合に読んでみれば、この先の宮本氏の言説は見通しがはっきりしてくる。一見、ごく一般的な判断のように書かれているところに、以前から引っかかりを感じたものである。
そして、それを普遍的な創造として成立させるためには、すでに述べたとおり、共同世界への絶えざるまなざしによって導かれることが必要であり、これこそ作品の普遍的な了解性を保証するものであるが、もし、それが失われれば、実存の深化は一転して実存の衰弱ないし貧困となり、そのときには、もはやいっさいの了解を拒否する奇妙な想念の遊戯か、あるいは、浅薄な社会性・外向性をもつだけの弛緩した製作物しか生み出すことができなくなる。たとえば、あれほど深い生存層からの「叫び」をあげたムンク(引用者註、ノルウェーの画家。『叫び』という絵は、ブームになったくらい有名)も、病いから脱してからは、外界の事物を写すだけの、密度を欠いた作品が多くなる。病いの後で寛解に達してからの創造物の価値が、病のなかでのそれに比べて、かえって急に低落する例は少なくない。この立論は一般的に概括できる性質を持っていない。多くの臨床例をもとにして、妥当な範囲で言えそうなことが書いてある、という性質のものだと思うから、ぼくのような非専門家が立ち入ってものを言っても差し支えないだろうと判断している。話題が、専門領域からずいぶんはみ出したところに展開して来るのである。だからだろう、宮本氏の結語は慎重な姿勢をとっている。
このように、分裂病の場合、創造の結実は、むろん天賦の才を前提とするものではあっても、社会的現実からの離脱と実存性の深化との微妙な均衡の上に成り立つといえるが、他方、芸術的不毛に至る危険をもみずからのうちに秘めていることは、彼らの本質的な悲劇性を物語るものであろう。ムンクなどの実在の症例が鮮やかだから、読み物として非専門家にもアピールする要素が宮本氏の著作にはある。変わった症例が載っている精神医学誌は別に珍しくないが、ぼくが宮本氏に興味を持つのは、難解な議論が見当たらないためである。だから、読後感想としてでも言いたいのだが、「病気」と「健康」という二項対立を問題にする前に確かめたほうがいい現実の更新がありうるだろう。「いっさいの了解」を容認しながら「弛緩し」ていない心理状況や創作や日常は存在する。それが病かどうかは、別の論議が必要である。これは素人の独りよがりの思い込みや、単なる無知のたぐいなのか、識者のご賢察を乞う次第です。
(宮本忠雄『言語と妄想』平凡社ライブラリー、220~224ページ)
最初のページにもどる
◆そもそも太鼓堂とは何か ◆音が聴けるページ ◆CD『江村夏樹 云々』 ◆太鼓堂 CDR屋さん ◆太鼓堂 DVDR屋さん
◆No Sound(このページには音がありません) ◆江村夏樹 作品表 ◆太鼓堂資料室 ◆太鼓堂 第二号館 出入り口
◆いろいろなサイト ◆江村夏樹『どきゅめんと・グヴォおろぢI/II 』